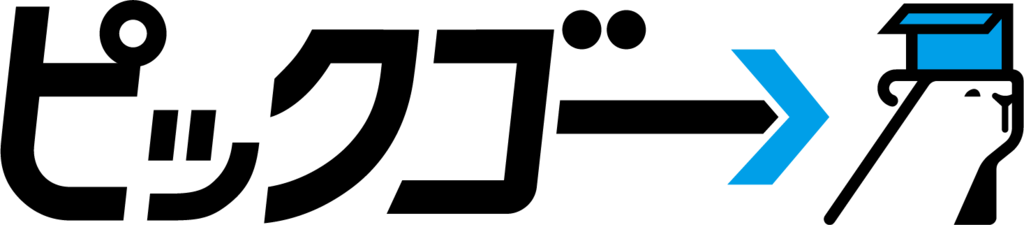3PLとは?導入のメリット・デメリット、事業者に依頼する際のポイント
こんにちは。物流に関する知識をまとめたメディア「ピックゴー物流コラム」編集部です。
EC市場の拡大や消費行動の多様化により、物流の重要性が増すとともに人材不足やコストの増大などの課題も浮き彫りになっています。そこで活用されているのが、3PLという戦略です。物流業務をアウトソーシングすることで、自社の負担を減らし業務効率化を図ります。
今回は、そんな3PL戦略の基礎知識や導入のメリット・デメリットを解説します。事業者を選ぶ際のポイントにも触れますので、物流業務の効率化や販路拡大にお悩みの場合はぜひ参考にしてみてください。
3PLとは?

物流現場で耳にする機会が増えた「3PL」。物流改革や生産性向上を目的に、業務のアウトソーシングを検討する企業も少なくありません。初めに、3PLの概要や導入が進む背景をお伝えします。
▸関連記事①:EC市場の拡大に伴い複雑化する「EC物流」の基礎知識と課題は、こちらの記事で詳しく解説しています。
▸関連記事②:物流全体を最適化する「3PL」と、EC運営に必要な全業務を担う「フルフィルメント」の違いを深く理解する。
3PLの意味
3PLとは、荷主企業が物流部門の業務を包括的に外部の物流会社に委託する業務形態のこと。「Third(3rd) Party Logistics」の略語で、「サードパーティ・ロジスティクス」と読みます。メーカーや荷主を「ファーストパーティー」、問屋や小売店を「セカンドパーティー」とした場合、物流会社は「サードパーティー(第三者)」に相当することに由来しています。3PLには、事業者が物流サービスの提供に必要な資産を保有している「アセット型」と、保有していない「ノンアセット型」の2種類があるのが特徴です。

3PLの導入が進む背景
インターネットの普及やEC市場の拡大により、企業における物流部門の重要性は増しています。しかし、自社で一からロジスティクスを構築するのは膨大な時間とコストがかかる上、商品を輸配送するたびに物流業者に依頼するのは非効率的です。
特に人材やトラックなどの輸送手段、荷物を保管する物流センターの確保、ソフトウェアの導入などにかかる時間やコストは、企業にとって無視できない問題です。そこで、荷主企業の物流業務全般を外部委託し、物流効率化と配送品質の向上を進める3PLという考え方が広まりました。
▹3PLは物流アウトソーシングの一種です。より広範な「物流アウトソーシング」のメリットとデメリットはこちらで詳しく確認しましょう。
3PLを導入するメリット・デメリット

3PLは、人手不足や物流コストの増大など物流業界が抱える課題の解決に役立つ仕組みです。一方で、ノウハウの蓄積や委託する業務の範囲など運用に関しては注意点もあります。以下では3PLを導入するメリット・デメリットを解説します。
メリット
コア業務に注力できる
3PLを活用すれば、物流業務に回していた経営資源(ヒト・モノ・カネ)をコア業務(本業)に充てることが可能です。商品開発やプロモーション、営業などのコア業務にリソースを集中することで、生産性の向上や事業成長の加速につながります。
コスト削減につながる
物流業務を外注することで人件費や物流拠点の維持費、運送費などの固定費を変動費化することができ、荷物の発送が少ない時期のコスト削減が可能です。物流にかかるコストを「見える化」できるため、キャッシュフローの改善にも役立ちます。また、在庫管理を行う3PL事業者に依頼することで不良在庫の削減も期待できるでしょう。
配送品質や顧客満足度を向上させやすくなる
ノウハウや経験の豊富な3PL事業者にアウトソースすることで、良好な状態での商品の納品やリードタイムの短縮などが実現できるため、配送品質や顧客満足度の向上が見込めます。企業に対する評価が高まり、利益の最大化や優秀な人材の確保もしやすくなります。
販路を拡大しやすくなる
物流業務を包括的に外注できれば人材の確保や育成などのハードルが下がり、販路を拡大しやすくなります。実店舗からECへ販売チャネルを増やす場合には、3PL事業者の持つノウハウを活用できるケースも考えられます。
労務リスクの軽減に役立つ
3PLの活用によって自社で担う物流業務を減らすことで、長時間労働や人間関係のトラブルなど物流現場が抱える労務リスクの軽減が可能です。企業のイメージアップにもつながり、魅力的な人材が集まりやすくなります。
デメリット
ノウハウを自社に蓄積しにくい
3PLでは物流業務全般を外部に委託するため、ノウハウを自社に蓄積しにくい傾向にあります。将来自社で物流を行う予定がある場合は注意が必要です。発送業務や流通加工業務など、一部の業務のみをアウトソースする方法も検討すると良いでしょう。
コア業務と委託業務の線引きが難しい場合がある
3PLを導入する場合は、どの部分を3PL事業者に任せ、どこを自社で行うのか明確にする必要があります。自社で行うべきコア業務まで委託してしまうと、品質の低下によって売上に影響するおそれもあり本末転倒です。しかし委託範囲の線引きは難しく、中核業務まで委託していたというケースも珍しくありません。
3PL事業者からの最適化施策の提案を期待できないことがある
3PLでは、荷主企業の物流改革が3PL事業者の利益減少につながる可能性があります。そのため、事業者からの積極的な最適化施策の提案を期待できない場合も多く、コストに見合う効果を得られないケースもあります。
3PL事業者に依頼する際のポイント

物流戦略の一環として3PLを活用する場合は、どのような基準で事業者を選べば良いのでしょうか。ここでは4つのポイントを解説します。
委託する業務の範囲を確認する
3PL事業者に委託できる業務は、検品・入庫、保管、仕分け、ピッキング、梱包、出荷の主に6つに分類されます。一部の業務をアウトソースする場合は、自社の強みや弱みを把握した上でどこまで任せるのかを検討しましょう。
繁忙期や閑散期に合わせて柔軟な対応ができる事業者を探す
荷主企業には、出荷数の増える繁忙期と、減少する閑散期があります。そのため、物量の波動に合わせて柔軟に対応できる事業者を選ぶことが重要です。特に、繁忙期に十分な人員を配置できないと人手不足から発送の遅延や誤配送が生じ、顧客からの信頼や売上の低下につながります。
サービス内容とコストのバランスを見極める
サプライチェーンにおける物流業務が重要性を増したことで、数多くの3PLサービスが登場しています。料金が安価な一方でカスタマイズ性の低いサービスや価格は高いものの、自社の課題とニーズを把握した上でサービスの提案を受けられるものなど。事前に予算と解決したい課題を確認しておき、サービス内容とコストのバランスに優れた事業者を選びましょう。
情報共有に関する指針を事前に定める
物流現場の抱える課題や問題点を解決し、納得できる物流サービスを提供してもらうには、荷主企業と物流事業者間のコミュニケーションが重要です。トラブルが発生した場合も、情報共有の手段が整っていなければ対処が遅れる可能性もあります。信頼できるパートナーとして連携を進めるためにも、事前に情報共有に関する指針を定めておくと良いでしょう。
▹3PLの検討と併せて、発送業務のみを外注する「配送代行業」の活用メリットを比較検討する。
3PLを効果的に取り入れて物流品質を向上させよう

3PLは、物流コストの増大や人手不足などの課題を抱える荷主企業にとって有用な戦略のひとつです。しかし、物流業務を丸投げするのでは効果の最大化は期待できず、かえって物流品質の低下などを招くおそれもあります。自社がイニシアティブを握りながら物流会社と連携し、より良いサービスを提供しましょう。
ピックゴーを活用した物流面からのビジネス支援
配送コストの最適化や物流業務のアウトソーシングをご検討の際は、「ピックゴー」の物流ソリューションをご利用ください。貴社ビジネスに合わせた新しいモノの流れの構築をご提案いたします。