
運送の単価が安い理由とは?利益を残すための単価改善術
目次[非表示]
- 1.「単価が安い…」と悩む運送会社に共通する4つの理由
- 1.1.理由①|多重構造でマージンが積み上がる仕組み
- 1.2.理由②|荷主と直接つながれず、条件交渉ができない
- 1.3.理由③|仕事を選べず、採算の悪い案件を抱えてしまう
- 1.4.理由④|稼働のムラで“仕方なく安い案件を受ける”状況が生まれる
- 2.単価を改善するために必要な3つの視点
- 3.単価を上げるための4つの具体策
- 3.1.①荷主との距離を縮める(紹介・横展開・直請け比率アップ)
- 3.2.②空車・帰り便のロスを減らし“低単価案件に頼らない体制”を作る
- 3.3.③得意領域を特化させ、単価UPしやすい案件に誘導する
- 3.4.④単価・条件が事前にわかる“配送プラットフォーム”を活用して案件の質を上げる
- 4.単価改善における配送プラットフォーム活用のメリット
- 5.ピックゴーが単価改善に強い理由
- 6.【実例】単価改善に成功した運送会社のケース
- 7.まとめ:単価改善の鍵は“案件を選べる状態”をつくること
「単価が安すぎて利益が残らない」
「距離や拘束時間の割にまったく割が合わない」
「条件の良い案件を取りたいのに、今の取引先では限界がある」
こうした悩みを抱える運送会社は数多く存在します。特に中小の一般貨物事業者からは「走っても走っても利益が出ない」「単価を上げたいと思っても荷主と直接つながれない」という声が非常に多く、単価の問題は構造的な課題と言えます。
この記事では、運送会社が「単価が安い状態から抜け出せない理由」を整理し、そのうえで今日から取り組める単価改善策を体系的にまとめています。
また、単価改善の手段の1つとして、全国の運送会社が活用している配送プラットフォーム「ピックゴー」の特徴についても紹介します。
単価改善にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
「単価が安い…」と悩む運送会社に共通する4つの理由
理由①|多重構造でマージンが積み上がる仕組み
一般貨物業界は運賃が多重に積み上がりやすい構造になっています。元請けから二次請け、三次請けと依頼が下りていく中でマージンが重なり、最終的に現場の運送会社に届く単価は圧縮された状態になります。20,000円の案件でも多重構造によって12,000円台になることもあり、この構造が続く限り利益が残りにくくなります。
理由②|荷主と直接つながれず、条件交渉ができない
多くの運送会社は荷主と直接取引ができていないため、「単価を上げたい」という交渉すらできません。下請け構造の中にいると単価は固定され、交渉の余地がないまま仕事を受け続けることになり、結果的に単価の改善が難しくなります。
理由③|仕事を選べず、採算の悪い案件を抱えてしまう
「仕事が少ないから仕方ない」「今断ると次から呼ばれなくなる」といった理由で、条件の悪い案件を引き受けざるを得ない状況が続きます。採算の悪い案件を抱え続けることで、走っても走っても利益が残らない状態になってしまいます。
理由④|稼働のムラで“仕方なく安い案件を受ける”状況が生まれる
午前だけ依頼が集中し午後は空車になる、月初は忙しいが中旬は暇になるなど、稼働にムラがあると安い案件でも「埋められるなら受けてしまう」という判断になりがちです。空車が多いほど単価の低い案件を受けざるを得ない構造が生まれます。
単価を改善するために必要な3つの視点

車両1台の“採算ライン”を正しく把握する
大型、4t、2t、冷蔵冷凍など車両ごとに採算ラインは異なります。走行距離、人件費、燃料、保険、拘束時間、荷扱い負担などを踏まえ、「赤字ライン」「最低限の採算ライン」「理想の単価ライン」を明確にすることで、どの案件を選ぶべきか判断できるようになります。
低単価の原因を可視化する(距離・拘束・荷扱い)
距離の割に単価が低い、拘束時間が長すぎる、荷扱いが重い、人員が必要なのに単価が一定など、単価が低い原因を可視化することで改善すべきポイントが明確になります。原因が整理されると不採算案件を避けやすくなります。
“選ばない勇気”を持つために案件の幅を広げる
単価改善の根本課題は「選べないこと」です。案件の入口が少ない状態では、低単価でも受けるしかありません。紹介、横展開、新規荷主、配送プラットフォームなど案件の入口を増やすことで、単価の悪い案件を避けられる“選べる状態”を作ることができます。
単価を上げるための4つの具体策
①荷主との距離を縮める(紹介・横展開・直請け比率アップ)
荷主と直接つながることができれば単価は自然と適正化しやすくなります。既存荷主の別拠点紹介、倉庫会社や物流企業との横連携、地域企業への訪問など、紹介営業は特に成功率が高く取り組みやすい方法です。
②空車・帰り便のロスを減らし“低単価案件に頼らない体制”を作る
空車時間が多いと安い案件でも受けざるを得ない状況になります。午後のみスポット案件を入れる、帰り便を確保する、稼働時間を細かく分割するなど工夫次第でロスは大幅に減ります。稼働率改善は単価改善の土台になります。
③得意領域を特化させ、単価UPしやすい案件に誘導する
精密機器、建材、冷凍冷蔵、長距離などは専門性が高く単価が高い傾向があります。得意領域を発信し、案件選択に反映することで高単価にシフトしやすくなります。
④単価・条件が事前にわかる“配送プラットフォーム”を活用して案件の質を上げる
案件情報が多く単価や条件が事前にわかる仕組みは、無理な案件を避けるうえで非常に有効です。料金、拘束時間、車格、荷扱い条件が明確で、自社に合う案件のみを選択できます。結果として案件の質が向上し企業全体の単価改善につながります。
単価改善における配送プラットフォーム活用のメリット
単価・条件が事前に見える“透明性”
従来の受注では「走ってみないと条件がわからない」という曖昧さが大きなリスクでした。配送プラットフォームでは単価、距離、所要時間、荷扱い内容などがすべて事前に提示され、採算性を正確に判断できます。これにより赤字案件や不合理な負担を避けられ、条件の良い案件に集中できます。
案件の質を選べるので“無理な案件”を避けられる
選択肢が少ない状態では低単価案件を受けざるを得ませんが、多様な案件が並ぶ配送プラットフォームなら、距離、時間帯、荷扱い、車格ごとに自社に合う案件だけを選択できます。「選べる状態」が整うことで低単価から抜け出しやすくなります。
得意領域・車格別で単価の良い案件にアクセスできる
冷凍冷蔵、精密機器、建材、長距離など専門性の高い案件は単価も高い傾向があります。配送プラットフォームでは案件が細かく分類されているため、自社の強みや車格にマッチした案件を選びやすく、自然と高単価市場へアクセスできます。
結果として、平均単価UPにつながる
低単価案件への依存が減り、高単価案件にアクセスできる機会が増えるため、会社全体の平均単価が上昇します。案件の選択肢が増えることで稼働の最適化も進み、長期的に利益率の向上が期待できます。
ピックゴーが単価改善に強い理由
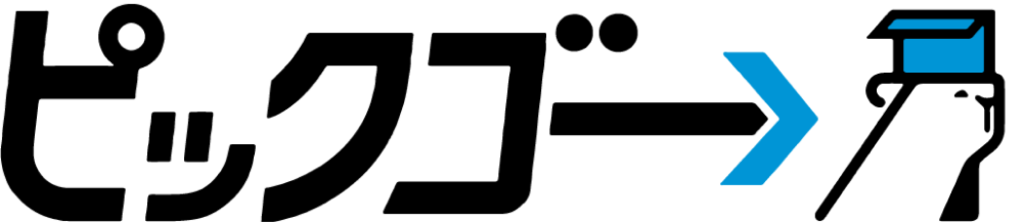
単価・条件の透明性が高い
ピックゴーでは単価、距離、荷扱い、必要人員など案件に関わる情報がすべて事前に可視化されています。現場でのギャップやトラブルが起きにくく、採算性をもとに案件を選べるため、単価改善の基盤が整います。
スポットと定期で単価の良い案件を柔軟に選べる
ピックゴーには高単価を狙いやすいスポット案件と、売上を安定させる定期案件の両方が存在します。状況に応じて使い分けることで単価を引き上げながら稼働の安定化も可能になります。
荷主直結の配送インフラだから余計な中間コストがかかりにくい
従来の複数社を挟む構造ではマージンが積み重なり現場に届く単価が低くなりがちですが、ピックゴーは荷主と運送会社が直接つながる配送インフラとして機能しており、中間搾取の発生を抑えた適正な単価が反映されやすいのが特徴です。
得意車格や強みを活かせる案件が取りやすい
2t、4t、冷凍冷蔵、建材、長距離など得意車格や専門領域に合わせた案件を選ぶことで単価UPがしやすくなります。案件の選択肢が広がることで、ドライバー負担も最適化され、高品質な運行に集中できます。
【実例】単価改善に成功した運送会社のケース
事例01 : 有限会社Dream KEI(東京都):保有車両数:20台

空車率65〜75% → 稼働率90%超へ!
隙間時間の有効活用で、車両が“常に稼働”する体制を実現
導入前の課題
- 1日の稼働スケジュールに“隙間時間”が多く、空車率は約65〜75%
- 車両を持っていても稼働が安定せず、収益のムラが大きかった
導入のきっかけ
- ピックゴーの「空いた時間を有効活用できる仕組み」に共感
- 自社の稼働率改善と新しい案件獲得チャネルとして導入
導入後の成果
- ピックゴー経由の案件活用で空車率がほぼゼロ
- 現在では約90%以上の時間が稼働で埋まり、収益が安定化
- ドライバーのモチベーションも向上し、柔軟な働き方が実現
事例02 : SAKAE株式会社(神奈川県):保有車両数:50台

コース単価が平均1.5倍にアップ!
若手中心チームがデジタルで新しい配送スタイルを実現
導入前の課題
- 単価が低く、車両1台あたりのコース単価が上がらない
- 既存の定期案件では収益が頭打ち
導入のきっかけ
- 「コース単価を上げたい」という目的でピックゴーを導入
- 空き時間を活用しながら、新しい受注ルートを広げる狙い
導入後の成果
- ピックゴー経由の案件でコース単価が平均1.5倍に向上
- 隙間時間にチャーター案件を柔軟に組み込めるようになり、配車ロスを削減
- 長距離便の戻り便確保にも成功し、収益効率がさらに改善
まとめ:単価改善の鍵は“案件を選べる状態”をつくること
単価が安い状態から抜け出せない理由は、努力不足ではなく構造的な問題にあります。単価改善の鍵は案件の入口を増やし、選べる状態を作ることです。
空車を埋める、帰り便を確保する、得意領域を活かす、条件の良い案件にアクセスする。これらはすべて単価改善につながります。
配送プラットフォーム「ピックゴー」は、単価の透明性が高く自社に合う案件を選びやすいため、単価改善の手段として非常に有効です。まずは自社の車格や得意領域でどんな案件があるか確認してみることをおすすめします。



