
運送会社の働き方を柔軟に。稼働の自由度を高める3つの戦略
目次[非表示]
- 1.なぜ今「稼働の自由度」が重要になっているのか
- 1.1.人材不足で、一人ひとりの負担が重くなっている
- 1.2.「収入の柱」を複数持つ必要性が高まっている
- 1.3.労働時間規制(2024年問題)への対応
- 1.4.ドライバーの“働き方の希望”が多様になっている
- 2.運送会社が抱える“柔軟に働けない理由”
- 3.稼働の自由度を高める3つの具体戦略
- 4.柔軟稼働における配送プラットフォーム活用のメリット
- 5.ピックゴーが“自由度の高い稼働”に強い理由
- 5.1.①スポット案件が豊富で、“スキマ稼働”に合わせやすい
- 5.2.②時間帯・車格・エリアを細かく指定して選べる
- 5.3.③定期案件もあり、「柔軟さ」と「安定」の両方をとれる
- 5.4.④アプリ・WEBで案件が届き、アナログなやりとりが減る
- 6.【実例】単価改善に成功した運送会社のケース
- 7.まとめ:自由な稼働を実現するカギは“選べる状態”をつくること
「働き方の自由度を上げたい」
「ドライバーの希望に合わせてシフトを組みたい」
「空いた時間だけ、ムリなく走らせたい」
「定期案件だけに頼るのは、会社としてリスクが大きい気がする」
そんなモヤモヤを抱えている運送会社は、この数年で一気に増えています。
背景には、ドライバーの働き方の多様化や、いわゆる“2024年問題”に代表される労働時間の規制強化、人材不足による一人あたりの負担増など、現場を取り巻く環境の変化があります。
特に中小の運送会社では、限られた人数と台数で毎日のスケジュールをやりくりしなければならず、「本当はもっと柔軟に稼働を組みたいけれど、現実的に難しい」という声をよく耳にします。
この記事では、運送会社が抱えがちな「稼働の自由度が低い理由」をいったん整理したうえで、今日から少しずつ実践できる“3つの戦略”として改善策をまとめました。
あわせて、すでに柔軟な稼働を取り入れている運送会社の事例や、そうした働き方と相性の良い配送プラットフォーム「ピックゴー」の活用イメージも紹介します。
「働き方の選択肢を増やしたい」「スポット案件をうまく使って負担をならしたい」「夜間や週末だけの稼働を増やしていきたい」と考えている方は、ぜひ読み進めてみてください。
なぜ今「稼働の自由度」が重要になっているのか
運送業界では、これまで以上に“働き方の柔軟性”が求められるようになりました。背景には、次のような事情があります。
人材不足で、一人ひとりの負担が重くなっている
長く続くドライバー不足の影響で、一人あたりの仕事量が増えています。固定のコースや時間帯に稼働が張り付いていると、急な欠員や増便に対応しきれず、残業や無理な稼働が発生しやすくなります。
「誰か一人抜けただけで全体が回らなくなる」──そんな綱渡りの状態から抜け出すには、稼働の自由度を高める工夫が欠かせません。
「収入の柱」を複数持つ必要性が高まっている
定期案件を1社・1ルートに集中させていると、減便や契約終了といった“想定外”の出来事が、会社全体の売上に直結します。
そうしたリスクを下げるには、
メインの定期案件
それを補完するスポット案件
時間帯や曜日の異なる別ルート
といった形で、収入源を分散させておくことが重要です。そのベースになるのが「自由に稼働を組み替えられる状態」です。
労働時間規制(2024年問題)への対応
拘束時間の管理がこれまで以上にシビアになり、従来のような“長時間当たり前”の働き方を続けることは難しくなりつつあります。
「これまで通り頑張れば何とかなる」では通用しにくくなり、
稼働時間をどう配分するか
限られた時間でどう売上を確保するか
といった「働き方の設計」が、より重要になってきました。
ドライバーの“働き方の希望”が多様になっている
昼間は別の仕事をしている副業ドライバー、家庭の事情で週3日までに抑えたいドライバー、夜間だけ働きたい人──。
働く側のライフスタイルや価値観が変わる中で、会社も柔軟な仕組みを用意できなければ、採用も定着も難しくなっていきます。
「うちの会社は、このスタイルしかない」ではなく、「こういう働き方も用意できる」という選択肢をどれだけ増やせるかが、これからの大きなポイントです。
運送会社が抱える“柔軟に働けない理由”

稼働の自由度を高めたいと考えていても、「現実的に動かせない」と感じている会社も多いはずです。その背景には、次のような事情があります。
①定期案件に縛られて、スケジュールが身動きしづらい
多くの運送会社では、売上の柱となる定期案件に合わせてスケジュールが固定されています。特に「朝から夕方までびっしり」という稼働があると、前後の時間に別の案件を入れにくくなり、日々の調整が難しくなります。
「空いている時間はあるのに、うまく組み合わせられない」という状態が続くと、稼働の自由度は上がりません。
②急な欠員対応に追われ、毎日が綱渡り
ドライバーの体調不良、急な家庭の事情、車両トラブルなどが起きれば、その穴を誰かが埋めなければなりません。
常にギリギリの人数で回していると、欠員のたびに他のドライバーへしわ寄せがいき、「毎日が綱渡り」のような状態になってしまいます。この状況では、「新しい働き方を試してみよう」という余裕を持つことすら難しくなってしまいます。
③稼働の“波”が大きく、計画が立てづらい
依頼の量は、曜日や時間帯、月によって大きく変動します。月初や月末だけ極端に忙しい、夕方だけ依頼が集中する、繁忙期と閑散期で差が激しい、、、といったことは、どの会社でも起こり得ます。
この“波”にそのまま振り回されていると、計画的な稼働の組み立てはどうしても難しくなります。
④案件情報の取得方法がアナログで、選択肢が広がらない
FAXや電話でのやり取りに頼っている場合、「知らない案件」にはそもそも出会えません。
「紹介された範囲の中だけで何とかする」という状態では、自社の方から働き方を設計することができず、いつまでたっても“選べる側”にはなれません。
柔軟な働き方を実現するには、案件の情報そのものを広く、リアルタイムで得られる仕組みが必要です。
稼働の自由度を高める3つの具体戦略
ここからは、今日から少しずつでも取り入れられる「3つの戦略」を紹介します。
①スポット案件をうまく組み込み、“柔軟な稼働枠”をつくる
スポット案件は、稼働の自由度を上げるうえで、とても扱いやすい選択肢です。
たとえば、次のような組み立てができます。
平日の午後だけスポットを入れる
本業は日中、夜間だけ別のドライバーが走る
土日だけ稼働したいドライバーにスポットを割り当てる
基本の定期便+空いた時間だけ追加でスポットを受ける
ポイントは、「今ある定期のスケジュールを崩さず、その“隙間”に柔軟に入れ込む」という考え方です。
スポット案件の枠をうまく作っておくと、
忙しい週は稼働を増やす
余裕を持たせたい週はあえて抑える
といった調整がしやすくなり、会社としての“調子を整える余白”が生まれます。
②複数の案件ルートを持ち、リスクと縛りを減らす
1社の定期案件だけに依存していると、その案件の動きに振り回されやすくなります。減便や終了のリスクが大きいのはもちろん、「決まった時間は必ず稼働しなければならない」という縛りも強くなります。
一方で、複数の案件ルートを持っていれば、次のような調整がしやすくなります。
忙しい週はC社の案件を増やす
ドライバーの希望に合わせて、A社とB社の案件を入れ替える
繁忙期はルートを組み替えて、空きが出ないように調整する
“自由度を高める”というと新しいことを始めるイメージがありますが、実は「依存度を下げる」という考え方も同じくらい重要です。
③“案件を選べる状態”をつくり、自由な働き方の土台にする
柔軟な稼働を実現しようとするとき、一番のネックになるのが「仕事を選べない状況」です。
条件があいまいなまま受けてしまう
走ってみたら拘束時間が長く、自由時間がきれいになくなる
結果として、会社もドライバーもヘトヘトになる
こうした状態から抜け出すには、「事前に条件が見える状態」をつくることが欠かせません。
時間帯、単価、車格、荷扱い、距離などが事前に見えていれば、
今日はこのドライバーの空き時間に合う案件を選ぶ
この日は稼働を抑えたいから、あえて案件を入れない
夜だけ別のドライバーに割り振る
といった判断がしやすくなります。
“柔軟な働き方”の前提には、「情報が透明であること」と「選択肢があること」がセットで必要だと言えます。
柔軟稼働における配送プラットフォーム活用のメリット
ここからは、柔軟な稼働を実現するうえで、配送プラットフォームを活用するメリットを整理していきます。
①時間帯・曜日を、自社の都合で選べる
配送プラットフォーム上には、「深夜のみ」「早朝のみ」「午後だけ」「週末限定」といった案件が多数流れています。
日中は既存の定期便に集中し、夜だけスポットを入れる
平日は抑えめにして、土日にしっかり走る
ドライバーの家庭の事情に合わせて稼働時間をずらす
といった組み立てがしやすくなり、会社とドライバー双方にとって“無理のない働き方”に近づけます。
②会社の状況に合わせて案件を取捨選択できる
人員状況やドライバーのコンディション、他の案件との兼ね合いなどを踏まえ、「今の会社の状態に合う案件だけを受ける」という判断ができます。
案件が多ければ多いほど、“断る勇気”も持ちやすくなります。選べる状態があることで、無理な働き方を避け、余裕のあるスケジュールを組みやすくなります。
③欠員補完にも使えて、リスクを下げられる
急な欠員が出たとき、固定のルートだけで対応しようとすると、結局別のドライバーにしわ寄せがいき、残業や連勤が増えてしまいます。
スポット案件をうまく活用すれば、
埋められなかった稼働を別日・別時間で補う
一部だけ別のドライバーに振り替える
といった柔軟な対応が可能になり、欠員によるダメージを最小限に抑えられます。
④稼働の“ムラ”を、意図的に埋められるようになる
午前だけ空いている日、夕方だけ車が余る日、特定の曜日だけ1台分の空きが出る週──。こうした細かな“隙間”は、どの会社にもあります。
配送プラットフォームを使えば、この隙間時間にうまく合う案件を探しやすくなり、「忙しいところは抑え、空いているところは埋める」という調整がしやすくなります。
結果として、稼働の波をならしやすくなり、ドライバーの負担も会社の収支も安定しやすくなります。
ピックゴーが“自由度の高い稼働”に強い理由
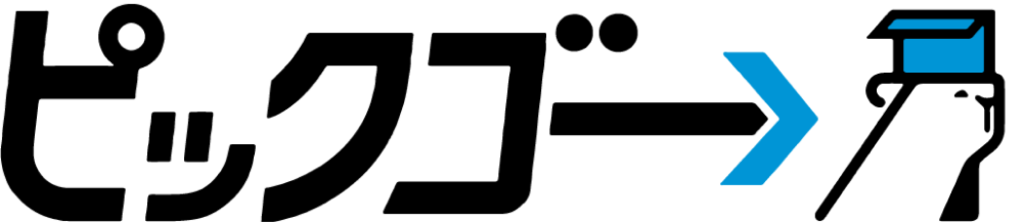
数ある仕組みのなかでも、配送プラットフォーム「ピックゴー」は、柔軟な働き方を実現したい運送会社と相性の良いサービスです。
①スポット案件が豊富で、“スキマ稼働”に合わせやすい
ピックゴーには、時間帯もエリアもさまざまなスポット案件が日々集まっています。
午後だけ空いている車両に
夜間のみ稼働したいドライバーに
繁忙期にだけ応援稼働を増やしたいときに
といった形で、「今のうちの状況」に合わせて柔軟に案件を組み合わせていくことができます。
②時間帯・車格・エリアを細かく指定して選べる
走行エリア、走りたい時間帯、対応可能な車格などを踏まえ、自社に合う案件だけをピックアップできます。
「行きたくないエリア」「今は無理な時間帯」の案件を無理に受ける必要がないため、会社として“譲れないライン”を守りながら働き方を設計できます。
③定期案件もあり、「柔軟さ」と「安定」の両方をとれる
ピックゴーはスポット案件のイメージが強いかもしれませんが、協力会社向けには定期的な案件も紹介されています。
定期案件で安定した売上をつくりつつ
スポット案件で空き時間や特定ドライバーの働き方を調整する
といった使い方ができるため、「柔軟性」と「安定性」を両立させやすいのが特徴です。
④アプリ・WEBで案件が届き、アナログなやりとりが減る
案件の確認・受注は、アプリやWEB上で完結します。FAXや電話のやりとりに割いていた時間が減り、「案件を探す」という作業そのものの負担が軽くなります。
その分、配車やドライバー対応など“本来やるべき業務”に時間を使えるようになり、結果的に会社全体の稼働の質が上がっていきます。
【実例】単価改善に成功した運送会社のケース
事例01 : 有限会社Dream KEI(東京都):保有車両数:20台

空車率65〜75% → 稼働率90%超へ!
隙間時間の有効活用で、車両が“常に稼働”する体制を実現
導入前の課題
- 1日の稼働スケジュールに“隙間時間”が多く、空車率は約65〜75%
- 車両を持っていても稼働が安定せず、収益のムラが大きかった
導入のきっかけ
- ピックゴーの「空いた時間を有効活用できる仕組み」に共感
- 自社の稼働率改善と新しい案件獲得チャネルとして導入
導入後の成果
- ピックゴー経由の案件活用で空車率がほぼゼロ
- 現在では約90%以上の時間が稼働で埋まり、収益が安定化
- ドライバーのモチベーションも向上し、柔軟な働き方が実現
事例02 : SAKAE株式会社(神奈川県):保有車両数:50台

コース単価が平均1.5倍にアップ!
若手中心チームがデジタルで新しい配送スタイルを実現
導入前の課題
- 単価が低く、車両1台あたりのコース単価が上がらない
- 既存の定期案件では収益が頭打ち
導入のきっかけ
- 「コース単価を上げたい」という目的でピックゴーを導入
- 空き時間を活用しながら、新しい受注ルートを広げる狙い
導入後の成果
- ピックゴー経由の案件でコース単価が平均1.5倍に向上
- 隙間時間にチャーター案件を柔軟に組み込めるようになり、配車ロスを削減
- 長距離便の戻り便確保にも成功し、収益効率がさらに改善
まとめ:自由な稼働を実現するカギは“選べる状態”をつくること
「稼働の自由度を高めたい」と考えたとき、最初に必要になるのは“案件を選べる状態”をつくることです。
スポット案件をうまく組み込み、複数の案件ルートを持ち、条件が見える仕組みの中で、自社に合う仕事を選んでいく。
この3つが揃うと、会社としてもドライバーとしても
「今週はこのくらいに抑えよう」
「このタイミングで少し上乗せしよう」
といった調整がしやすくなり、無理のない働き方に近づいていきます。
配送プラットフォーム「ピックゴー」は、そうした“選べる状態”をつくるための、ひとつの有力な手段です。スポットと定期を組み合わせながら、自社に合うスタイルで柔軟な稼働を設計することができます。
まずは、自社の車格やエリア、時間帯に合う案件がどのくらいあるのか。一度確認してみるところから、次の一歩が見えてくるはずです。



