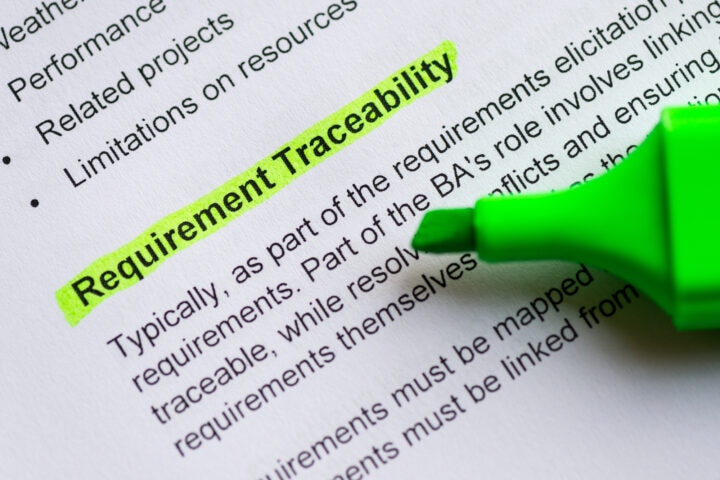
トレーサビリティとは?生産から廃棄まで商品を追跡可能にする仕組み
目次[非表示]
「トレーサビリティ」は、顧客の安全意識や商品の品質意識の高まりに応じて、近年注目を集めている単語です。物流業界や食品業界をはじめとした、商品の輸送や加工を担うさまざまな現場で導入が進んでいます。
今回は、トレーサビリティに関する基本知識や種類、導入のメリットなどについて解説します。最後には、トレーサビリティに利用される最新技術と合わせて、トレーサビリティの強化に役立つサービスも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
トレーサビリティの基礎知識

トレーサビリティとは?
トレーサビリティとは、商品の生産・製造から消費・廃棄されるまでの過程を追跡可能な状態にしておくことを意味しています。英語のトレース(Trace)とアビリティ(Ability)を組み合わせて作られた用語で、「Traceability」と表記します。日本語では「追跡可能性」とも訳され、製品の品質管理や安全管理には欠かせない単語です。トレーサビリティは国産牛肉やアメリカ産牛肉で発生した狂牛病(BSE)問題の事例を発端に国内でも広く注目されるようになり、食料品や医薬品、電子機器など幅広い分野で活用されている方法です。
例えば販売している電子機器に問題が発生した場合、トレーサビリティによって商品の記録情報を追跡すれば問題点をスピーディに特定できるようになります。また、消費者はどこで商品が作られたのか理解できるため、安心して購入することが可能です。そのため、顧客満足度を向上させるためにもトレーサビリティには重要な役割があります。
またトレーサビリティには、記録をたどる方向に応じて2種類の呼び方が存在します。時系列を遡及して履歴情報を確認するのがトレースバックです。出荷した商品に不具合があった場合、トレースバックによって問題のあるロットや工程の特定が速やかに行えるため、迅速な原因究明や課題の発見に役立ちます。
また、時系列に沿って商品を追跡することをトレースフォワードと呼びます。リコールや不良品など、問題の発生した商品を回収する際に用いられるのが一般的です。
トレーサビリティの必要性
トレーサビリティは、商品のトラブル対策や安全性を確保するために必要となります。商品の品質に問題が発生すると、企業・メーカーは消費者や取引先から信用を失って売上が低下してしまいます。企業としての存続ができない原因にもなりうるため、早急な対策が必要です。
トレーサビリティによって商品の全体的な流れを追跡できれば、どこに問題があったのか早急に把握できるようになります。問題点を特定できれば、消費者や取引先に説明をして商品の改善が可能です。とくに食料品や医薬品は健康面に関係する物なので、安全性の確保が求められます。現在では消費者の安全を保護する法律が成立されていることもあり、商品を提供する企業はトレーサビリティの取り組みが必要不可欠になっているのです。
トレーサビリティの仕組み
トレーサビリティにおいては、商品の流れを記録できる状態にしておくことが大切です。商品がいつどこで作られてどこへ届いたのかを記録することで、問題点の特定や改善を行えるようになります。例えば牛肉を取り扱う農業や食料品では、牛に「耳標」というタグをつけて個体管理をしています。
耳標には個体識別番号やバーコードがあり、牛肉として販売される工程でも記載が義務づけられているのです。これにより牛を取り扱う農業や牛肉の製造会社、物流会社、小売業者、消費者が記録情報を把握できるようになります。
万が一牛肉に問題があったときも記録情報から特定できるため、適切な対策を取ることが可能です。食料品だけでなく医薬品や電子機器も同じような記録情報が記載されており、各工程を追跡できる仕組みが作られています。
▹関連記事:製品の回収や廃棄の流れを追跡する「静脈物流」と「動脈物流」の違いと構築方法。
トレーサビリティが注目されている背景
トレーサビリティが注目されている背景には、商品の品質が大きく関係しています。2001年に国産牛肉が「BSE(狂牛病)」に感染したことにより、食料品の安全性を見直す必要性があると報告されました。そして2003年に農林水産省から「牛肉のトレーサビリティ」が発表され、全ての牛を識別・追跡できるように義務付けられています。
その後、食料品をはじめ医薬品や電子機器も品質を管理するためにも、工程記録を情報として残せる取り組みがされるようになりました。消費者が安全に過ごすためにも、トレーサビリティは大切な役割を持っているのです。
参考URL:農林水産省:牛・牛肉のトレーサビリティ
トレーサビリティの種類
チェーントレーサビリティ
チェーントレーサビリティとは、原材料や生産、加工、卸売、小売など、流通の各段階において、商品の移動を把握できる状態にしておくことを指します。複数の事業者間で互いに履歴を確認できるため、生産者は商品が加工されたり消費されたりした場所がわかり、消費者はこの商品がどのような経路でここまで来たのかわかる仕組みです。
チェーントレーサビリティを実施するためには、商品に関係する複数の企業が連携して情報共有することが大切です。各企業の方針や文化の違いによって情報共有がうまくいかないこともあるので、担当者は定期的に全体的なコミュニケーションを取る必要があります。
内部トレーサビリティ
内部トレーサビリティとは、ひとつの企業や工場内で部品や製品の移動を追跡可能な状態にしておくことを指します。チェーントレーサビリティとの大きな違いとして、内部トレーサビリティは特定の企業のみで商品の流れを管理します。
たとえば製造業の現場では、製品ごとに個体識別番号を付与して原料の入荷から製品の出荷までを管理したり、すべての工具や部品に2次元コードやバーコードを印字し、部品の活用状況や工具の摩耗具合などのデータを収集・蓄積したりしています。
トレーサビリティを導入するメリットと注意点

トレーサビリティを導入することで、以下のような5つのメリットがあります。
メリット
不良品の流出を防止できる
早急な対応ができる
顧客管理の負担を減らせる
ブランドイメージを向上できる
DX化を推進できる
それでは順番に解説します。
不良品の流出を防止できる
トレーサビリティシステムの導入は、商品の品質向上やリスク管理の効率化につながります。不良品の発生など商品に問題が起こった際に、発生箇所や原因を特定できるため、現場の意識を高めやすいのが理由です。詳細な原因を特定できれば、改善策を立てやすいでしょう。
またトレーサビリティによって商品の流れを管理すれば、不良品が消費者や取引先のもとへ届く前に回収することも可能です。商品を提供するまでには検査段階があるため、問題があった物は識別番号を通じて問題があった工程を特定できるからです。
問題がある工程をピンポイントで特定できれば、全体の業務効率を維持したまま改善を加えられます。結果的に商品の品質向上にもつながり、不良品の流出を防げます。不良品の回収費用もかからずに済むので、商品を製造する企業にとってもトレーサビリティのメリットは大きいです。
早急な対応ができる
トレーサビリティを実現すれば全工程の情報を蓄積できるため、問題が発生したときに早急な対応ができるようになります。例えば製造工程で問題が発生した場合、製造機器や従業員などが原因になっていないか素早く特定できます。
問題点が見つかれば早急な対応ができ、商品が消費者・取引先のもとへ届く前に対策方法を考えることが可能です。市場でのリコールが発生するリスクを防げるだけでなく、問題が発生したときに早急な対応ができる点はトレーサビリティを実施するメリットの1つです。
顧客管理の負担を減らせる
トレーサビリティは、商品が顧客のもとへ届いて消費されるまでの情報を記録できます。顧客の基本情報や購入履歴などの情報を蓄積できるため、顧客管理の負担を大幅に軽減することが可能です。
蓄積した顧客データを活用すれば、商品の需要率を各企業に情報共有して改善方法を考えられるようになります。ターゲットに合わせたマーケティング戦略立案ができるようになるので、顧客管理の担当者にとってもメリットとなるでしょう。
ブランドイメージを向上させやすい
トレーサビリティを導入することで、製品の原材料や工程をすべて開示することになるため、安心・安全な商品であることを消費者に証明でき、ブランドイメージの向上が期待できます。特に、食品トレーサビリティについては一般の顧客にも広く浸透しており、「どこで」「誰が」「いつ」生産・加工したものか確認したうえで商品を購入する方も少なくありません。
消費者や取引先は、商品を選ぶときに安全性や品質に注目しています。トレーサビリティを実施すれば、顧客が商品の情報をチェックできるので安全性や品質を把握できます。リスクに対する取り組みを紹介することもできるため、自社のブランドイメージを向上可能です。市場における他社との差別化を図れることから、商品の売上向上にもつながるでしょう。
DX化を推進できる
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がデジタル技術を取り入れて業務や文化、プロセスなどを改革する取り組みを指します。幅広い業界・業種でデジタル化が進む現代では、生産性・効率性を向上させるためにDX化が推進されています。
トレーサビリティはITシステムを導入することで、各企業と連携を取ることが可能です。例えば小売業者から販売・売上実績やPOSデータを共有してもらえば、各企業が顧客ニーズを予測しながら状況に合わせて原材料の調達・製造・発送などができるようになります。
ITシステムを扱える人材教育や導入コストは課題となりますが、DX化を推進できる点は各企業において大きなメリットといえます。
注意点

トレーサビリティを導入する際は、複数の企業間・部門間で連携できるようシステムを構築する必要があるため、インフラ構築にコストがかかります。また、導入後のトラブルを防ぐためにも、運用ルールなどを事前に細かく取り決めておかなければなりません。認識にズレがあると、問題発生時に追跡できなくなる可能性があります。
また、トレーサビリティの種類によって課題は異なるため、これから導入を検討しているならチェックしておきましょう。
チェーントレーサビリティの課題
チェーントレーサビリティでは、各企業の連携が大きな課題となります。企業によって方向性や文化が異なるため、価値観のズレによって連携がうまくできないケースがあります。
また、企業は自社の利益を優先する傾向にあるので、他社のためにどんな対応ができるのかも課題の1つです。このような課題を解決するためには、各企業が費用対効果を把握できるシステムの構築が必要です。費用対効果によって得られる成果を各企業が理解できれば、連携をしながらトレーサビリティを進められるようになるでしょう。
内部トレーサビリティ課題
内部トレーサビリティの課題には、現場で不要な作業が追加される恐れがあります。現場で不要な作業がトレーサビリティの情報に追加されてしまうと、情報収集が二重構造になる可能性が高いです。トレーサビリティは生産効率を向上できる点がメリットなので、構築するときはコミュニケーションを取りながら双方が納得して取り組めるようにしなくてはいけません。
取得する情報
トレーサビリティで取得する情報は、業界・業種によって異なります。例えば製造業界の場合、商品の入荷情報や製造情報、検査情報、担当者、生産ライン、出荷情報などを記載します。食品業界の場合、食品の生産者や産地、出荷情報、加工日時、賞味期限、出荷上場などを記載してください。
表現様式・伝達媒体・記録媒体
各工程の情報を記録するには、文字や数字、電子情報、バーコード、2次元コードなどを活用します。これらの表現方法を「表現様式」と呼び、商品に関する情報を伝達できるようになっています。
表現様式はあくまでも記号であるため、電子タグやラベルなどの「伝達媒体」も合わせて必要です。取り扱う製品によって、使用する表現様式や伝達媒体は異なります。例えば牛肉の場合、牛に付ける耳標が伝達媒体・表現様式になります。そして伝達媒体に記載されている表現様式の情報を管理するために、パソコンやクラウドサーバーといった「記録媒体」が必要になるのです。
トレーサビリティに利用される主な技術

GPS
GPSを利用した動態管理システムを利用することで、対象となる商品の現在位置や、過去の運行状況の記録を確認できます。中でも、CBcloud株式会社の提供する「SmaRyuトラック」がおすすめです。クラウド型サービスのため、全国どこからでも確認でき、GPSで細かく追跡可能です。また、専用アプリでドライバーに対してチャットで連絡を取れるため、緊急時の対応も万全です。請求書の発行手続きなど面倒な作業を一元化できる機能もあり、漏れやトラブルの防止にも役立ちます。
ブロックチェーン
ブロックチェーンとは、取引履歴などの情報を共有管理することで、改ざんや不正を行いづらくする技術です。SmaRyu Truckでは、車両の動態管理にブロックチェーン技術を活用することで、外部から改ざんされないセキュアなシステムを実現しています。
RFIDタグ
RFIDタグとは、非接触でデータの読み取りや書き取りができるICタグです。トレーサビリティにRFIDタグを組み合わせることで、商品の品質管理や在庫管理を効率良く行えるようになります。
▹GPSを利用した「動態管理システム」で実現する車両の追跡と運行状況の可視化。
トレーサビリティマトリクスとは
トレーサビリティマトリクスとは、各工程の流れを可視化するための表です。トレーサビリティマトリクスがあれば、不具合発生時に問題の特定や対応した方法などを把握できるようになります。
不具合の特定がスピーディになるため、全体の作業効率を向上させられます。トレーサビリティマトリクスの書き方については、以下の参考記事をご覧ください。
参考URL:トレーサビリティとは?その意味と管理の方法を解説
トレーサビリティの徹底はリスクマネジメントや顧客からの信頼獲得に必須

今回は、トレーサビリティが必要される背景や導入のメリット、トレーサビリティの徹底に利用される技術についてお伝えしました。トレーサビリティを導入することで、商品の安全性や作業工程の透明性をアピールすることが可能です。そのため、消費者が多くの選択肢から商品やサービスを選べる現代においては、トレーサビリティの徹底が必須といえるでしょう。
トレーサビリティは、不良品の流出防止や早急な対応、顧客管理の負担軽減、ブランドイメージの向上のDX化の推進などのメリットがあるため、幅広い業界・業種で注目を集めています。商品の顧客満足度を向上させたい企業の皆さまは、ぜひトレーサビリティの実施を検討してください。
ピックゴーを活用した物流面からのビジネス支援
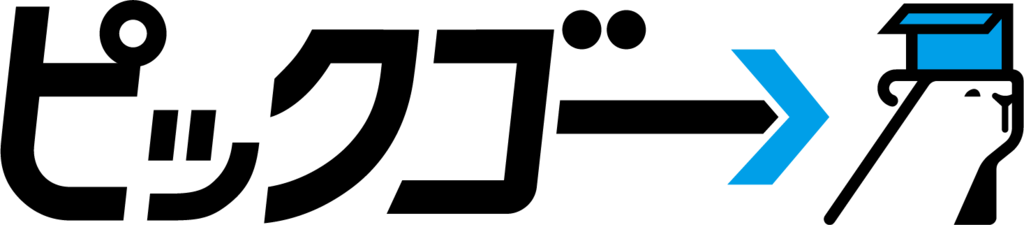
ここで物流課題の解決に貢献する、ピックゴーで提供している物流ソリューションの特徴を一部ご紹介します。配送プラットフォーム「ピックゴー」では配送状況をウェブ上で追跡できるため、配送という側面においてトレーサビリティに貢献します。
圧倒的な配送力
全国に100,000台の軽貨物配送パートナー、3,000社以上の一般貨物パートナーをもつピックゴーでは、多彩な輸送ネットワークを活用することが可能です。
独自のITノウハウ
多くの事業者さまのビジネスを最適化してきた実績もございます。自社開発のシステムやソフトウェアを活用し、御社だけの物流網を構築します。
ニーズへの対応力
急な荷物の増減=波動の吸収にも柔軟に対応。ご要望に応じたリードタイムを設計します。24時間/365日のサポート体制だから緊急時にも安心!
これまで幅広い業界でビジネスと伴走してきたピックゴーの配送力は、お客様の様々な問題を解決しています。多数の実績もご覧いただけますので、お気軽にご相談ください。



