
黒ナンバーの書類の書き方を解説!必要な手続きも紹介
こんにちは。物流に関する知識をまとめたメディア「ピックゴー物流コラム」編集部です。
黒ナンバー(軽貨物運送)で起業するためには、特定の書類の作成が必要です。この記事では、黒ナンバーの申請方法から取得できる条件、必要な書類や費用まで、黒ナンバーを取得して軽貨物運送事業を始めるまでのポイントを紹介します。
目次[非表示]
黒ナンバーとは?
「黒ナンバー」とは、軽貨物運送事業を営む際に必要な、特別なナンバープレートのことです。この黒色のナンバープレートは、軽貨物運送業務に使用する車両にのみ取り付けられます。黒ナンバーを取得しなければ、軽貨物運送事業を営むことはできません。
なお、黒ナンバーを取得できるのは、特定の車種に限られます。具体的には、軽自動車のうち軽貨物車(通称「軽バン」)や軽トラックなどが該当します。これらの車両は4ナンバーと呼ばれており、黒ナンバーを取得できる対象です。
▹書類作成の前提となる「黒ナンバーの取得手続きの全体像」を把握する。
軽貨物運送事業とは?

軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)は、軽貨物車を使用した運送業のことを指します。一方、中型トラックや大型トラックを使用する場合は「一般貨物自動車運送事業」となり、緑ナンバーの取得が必要です。また、「特定貨物自動車運送事業」は特定企業の運送のみを担う事業形態で、系列会社が許可を取得することが一般的です。
軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)は届出制であり、許可を待たずに始めることができるメリットがあり、個人事業主が1人で車両を所有し運送事業を始めることが比較的容易です。この事業形態は、1人と1台の軽貨物車で始められるため、スタートアップのハードルが低いと注目が集まっています。
黒ナンバーの申請方法
黒ナンバーの申請のためには、運輸支局と軽自動車検査協会の2ヵ所に書類を提出しなければならないので、必要書類の準備から始めましょう。なお、軽自動車検査協会に提出する必要書類に関しては記事の後半部分で紹介するので、ここでは運輸支局の必要書類のみを紹介しています。
下記の内容が運輸支局に提出する書類です。
- 車検証(新車の場合は完成検査証、使用する軽貨物車の車台番号が確認できるものが必要)
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用と控え用の合わせて2部必要)
- 事業用自動車等連絡書
- 運賃料金設定届出書(提出用と控え用の合わせて2部必要)
ここまでが運輸支局に提出する必要書類で、運輸支局に提出する車検証に関しては基本的にコピーでも構いません。
書類の準備ができたら、下記の順番で手続きにまわって黒ナンバーの取得を完了します。運輸支局と軽自動車検査協会は同じ敷地内にある場合が多いので、手続きは同日内で終わる場合がほとんどです。
- 運輸支局と軽自動車検査協会に提出する必要書類の準備
- 運輸支局で手続き
- 軽自動車検査協会で手続き
- 黒ナンバー取得完了
ここまでが黒ナンバー取得までの申請の流れです。必要書類の書き方などは記事後半の方で紹介しているので、ぜひ最後までご覧になってください。
黒ナンバーが取得できる条件
黒ナンバーを取得できる条件は下記のとおりです。
- 軽貨物車を1台以上保有している
- 営業所・休憩施設・車庫を保有している
- 運送約款を用意している
- 運行管理等の管理体制が整っている
- 損害賠償能力がある
まず、当たり前のことですが軽貨物車を1台以上所有していることが求められます。これは、貨物軽自動車運送事業を営むための最低限の要件です。軽貨物車の次に重要な営業所や休憩施設、車庫を所有していることも条件の1つです。これらの施設は、事業の運営に必要な基盤となるので、どれも欠かせません。
また、運送約款を用意していることも重要です。運送約款は、運送業者と顧客の間での契約条件を明確にするための文書です。運行管理や安全対策などの管理体制も整っている必要があります。これには適切なルート設計、車両点検・整備、ドライバーの安全教育などが含まれます。
最後に、損害賠償能力があることも要件の1つです。運送業は事故や損害が発生する可能性があるため、十分な賠償能力が求められます。
これらの条件を満たすことで、黒ナンバーの取得が可能です。取得条件を満たしていれば、運輸支局と軽自動車検査協会で必要な手続きを済ませることができます。
黒ナンバー取得に必要な書類<運輸支局に提出する書類>
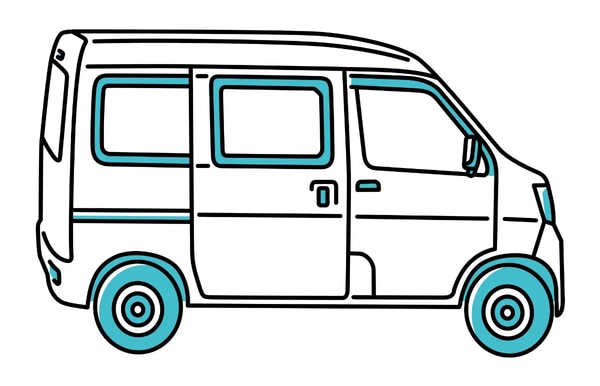
黒ナンバーを取得する際に運輸支局に提出する書類には下記のものがあります。
- 車検証(新車の場合は完成検査証、使用する軽貨物車の車台番号が確認できるものが必要)
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用と控え用の合わせて2部必要)
- 事業用自動車等連絡書
- 運賃料金設定届出書(提出用と控え用の合わせて2部必要)
ここでは、書類の書き方を紹介するので、必要な書類を用意する際に参考にしてください。
貨物軽自動車運送事業経営届出書の書き方
まず、貨物軽自動車運送事業経営届出書の記入方法について説明します。この届出書は貨物軽自動車運送事業を始める際に提出する必要があります。書類の作成には以下の項目の記載が必要です。
- 事業開始予定日
- 事業者の氏名、住所、電話番号など、基本的な情報
- 事業所の名称、住所などの情報
- 事業で使用する軽貨物車の車種と種類別の台数
- 事業で使用する軽貨物車の車庫の住所、営業所までの距離、車庫の面積
- 乗務員の休憩や睡眠施設の住所と面積
- 運動約款の該当する項目にチェック
- 事業所の住所と運行管理責任者の氏名
- 運輸支局長への宣誓書欄
貨物軽自動車運送事業経営届出書は、基本的に上記の項目の内容を記入します。項目ごとに記入する枠が設けられており、書きやすいので困ることはないでしょう。
事業用自動車等連絡書の書き方
続いて、事業用自動車等連絡書の記入方法について説明します。この連絡書も貨物軽自動車運送事業を始める際に提出する必要があります。書類の作成には以下の項目の記載が必要です。
- 事業の種別を項目から選びチェック(一般、貨物、軽、霊柩など)
- 開業する軽貨物車の使用者の名称と住所
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書に記載した事業所の名称と住所
- 使用する軽貨物車が新車の場合は「型式」(諸元表の写しを提示)
- 使用する軽貨物車が中古車の場合は「車体番号」(車検証等の写しを提示)
- 自動車の年式、乗車定員、軽貨物車の種別にチェックを入れて最大積載量
- 事案発生理由の項目の新規届出にチェック
事業用自動車等連絡書は、基本的に上記の項目の内容を記入します。貨物軽自動車運送事業経営届出書と同様に、項目ごとに記入する枠が設けられており、書きやすいので困るようなことはないでしょう。
運賃料金設定届出書の書き方
最後は、運賃料金設定届出書の記入方法について説明します。この届出書は、貨物軽自動車運送事業を始める際に、貨物軽自動車運送事業経営届出書や、事業用自動車等連絡書と合わせて準備する必要があります。書類の作成には以下の項目の記載が必要です。
- 運輸局に提出する日付
- 軽貨物運送事業者として開業する本人の住所、氏名、代表者名、電話番号
- 設定した運賃及び料金を適用する地域を3パターンから選んでチェック
- 設定した運賃及び料金の種類、額及び適用方法
※貨物軽自動車運送事業運賃料金表を作成する場合は、別添のとおりと記入 - 開業する年月日
運賃料金設定届出書の記入方法は、基本的に上記の項目の内容を記入します。
ここからは、別添で用意する場合もある「貨物軽自動車運送事業運賃料金表」の記入方法も簡単に紹介するので参考にしてください。
まずは、距離制運賃表の作成です。10kmまでの運賃を設定し、20kmや30kmの場合の運賃も個別に記入します。以降5kmを増すごとの運賃まで設定することができるので設定しておきましょう。
次に、運賃割増率の設定です。通常の運賃で、精密機器のような「易損品」と呼ばれるものや、高圧ガス取締法などに関連する「危険品」を運ぶとなると、普段以上に気を遣って運ぶ必要があるのでデメリットが大きいです。そのため、割増した運賃で請け負うことが一般的となっています。
運賃割増率の設定はほかにも「特大品割増」や「冬期割増」「休日割増」などがあり、設定次第で売上や受注率に影響のある大切な内容となるので、しっかりと考えて設定するようにしましょう。
黒ナンバー取得に必要な書類一覧<軽自動車検査協会に提出する書類>
引き続き、黒ナンバーを取得する際の申請に必要な書類を紹介します。こちらで紹介する内容は、軽自動車検査協会に提出する書類についてです。
- 車検証原本
- 使用する車両の黄色ナンバープレート(前後の2枚)
- 運輸支局の受領印が押された事業用自動車等連絡書
- 住民票(法人の場合は法人謄本)
- 申請依頼書(代理人が手続きをする場合に必要)
※軽自動車検査協会では書類のほかに印鑑が必要になります。
上記の内容が軽自動車検査協会に提出する必要書類です。運輸支局と大きく違う点は、車検証の原本が必要となる点、住民票や法人謄本などの役所関連の書類が必要な点です。
また、軽自動車検査協会で手続きする際に、ナンバープレートの費用として1,500円程度必要になる場合もあるので注意しましょう。
黒ナンバーの取得にかかる費用と時間
黒ナンバーの取得にはある程度の費用と時間がかかります。ここでは、どのような費用とどれくらいの時間を要するのかを説明するので、手続きの参考にしてください。
まず、黒ナンバー取得にかかる費用は下記のとおりです。
- ナンバープレート発行費用(1,500円程度)
- 車検証をコピーする費用(30円程度)
- 役所で住民票などを発行する費用(400円程度)
次に、黒ナンバー取得にかかる時間は下記のとおりです。
- 役所で住民票などを発行する場合の移動時間と待ち時間
- 運輸支局と軽自動車検査協会に行く移動時間と待ち時間
※同じ敷地内にない場合は、その分の時間も発生します)
上記の内容が黒ナンバー取得にかかる費用と時間の参考ですが、手続きを専門業者に代行してもらう場合は追加の費用がかかります。取得代行の費用としては3万円前後が目安なので、時間がない方や、手続きが面倒だと思う方は依頼してみるのもよいでしょう。
手続きが不安な方には「クロッキー」がおすすめ

ここまで黒ナンバーを申請するための書類の書き方などについて紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?正直なところ、文章だけでは、運輸支局や軽自動車検査協会に出向いて手続きするのが不安な方もいると思います。
そこで、軽貨物運送事業を始めるのにピッタリの「ピックゴー」をご紹介します。ピックゴーにパートナー登録して軽貨物運送事業を始めることで、案件を見つけやすくなるだけでなく、もしもの時に安心な黒ナンバー代車のサービスなど各種支援サービスを利用することが可能です。
すでに軽貨物ドライバーとして開業しようと考えている方は、ストレスフリーで開業できるのでおすすめです。
⇒車両売買サービス「 クロッキー」
⇒事業用軽貨物代車サービス「黒ナンバー車共同使用」




