
サプライチェーンマネジメント(SCM)を導入するメリットと流れ
こんにちは。物流に関する知識をまとめたメディア「ピックゴー物流コラム」編集部です。
サプライチェーンマネジメントは、サプライチェーンに関係するすべての企業で情報を共有することで、業務プロセスの最適化を図る手法です。企業のグローバル化や労働環境の変化、IT技術の進化などを受けて注目を集めています。
今回は、サプライチェーンマネジメントに関する基本的な知識や、導入によるメリットをご紹介します。サプライチェーンマネジメント向けのソリューションサービスを活用する際の流れも解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
サプライチェーンマネジメントの基礎知識
サプライチェーンマネジメントは「サプライチェーン管理」とも訳される、製造業や物流業界など、ロジスティクスの現場では欠かせない単語です。こちらでは、サプライチェーンマネジメントの特徴や注目されている背景などをご紹介します。
サプライチェーンマネジメント(SCM)とは?
サプライチェーンマネジメントとは、サプライチェーン全体で情報を共有し、製品の原材料の調達から販売までのすべての業務プロセスを効率化・最適化する経営管理手法のことです。サプライチェーンは商品が消費者の手元に届くまでのプロセスを意味する物流用語で、具体的には、原材料や部品の調達から、商品の生産、物流・流通、エンドユーザーへの販売という一連の流れを指します。「Supply Chain Management」の頭文字からSCMと略されることもあり、日本語では「供給連鎖管理」や「サプライチェーン管理」と訳されます。
サプライチェーンマネジメントが必要とされる背景
- 企業のグローバル化
企業のグローバル化により、調達や生産、販売のネットワークが世界中に広がっています。各プロセスにおけるデータや情報を個別に管理する状態のままでは、海外との競争に後れをとる可能性があります。そのため、サプライチェーンマネジメントを導入して、情報を一元管理する必要性が高まっているのです。
- 労働環境の変化
物流現場では、少子高齢化や生産年齢人口の減少などを受け、人手不足のリスクが深刻化しています。そのため、各企業は在庫管理システムや物流システムの導入、DX戦略を通して業務の効率化を求められており、サプライチェーンマネジメントはそれを支援する仕組みとして注目を集めています。
- コスト意識の高まり
日本の企業は、バブル経済の崩壊やその後の長期的な経済の低迷を経験し、収益構造の改善やコスト削減などの意識が高まっています。サプライチェーンマネジメントは、各プロセスの情報を共有することで在庫量の適正化やリードタイムの短縮によるキャッシュフローの改善などにつながるため、企業間での導入が進んだと考えられます。
- ビジネスモデルの変化
サプライチェーンマネジメントが求められる背景には、対面販売から通信販売(EC)へのビジネスモデルの変化も影響しています。EC市場では販売と配送の緊密な連携が重要となるため、両者を統合的に管理できるサプライチェーンマネジメントの構築が求められています。
- IT技術の進化
サプライチェーンマネジメントが注目を集める背景には、IT技術の進化により提唱された「インダストリー4.0」が影響しています。インダストリー4.0とは第4次産業革命を起こすための取り組みのことで、2011年にドイツが発表しました。インダストリー4.0の提唱により、物流や製造の現場では、ブロックチェーンやクラウド、AI、IoTなどのテクノロジーを活用し、サプライチェーンマネジメントのデジタル化を図ることが求められているのです。
【出典】「第1部 特集 人口減少時代のICTによる持続的成長」(総務省)
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd135210.html
サプライチェーンマネジメントとERPとの違い
ERPとは、「Enterprise Resources Planning」の略語で、「企業資源計画」のことです。具体的には、企業資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を有効活用することで効率化を目指す管理手法を指します。一方、サプライチェーンマネジメントは調達から販売までのプロセスのみに焦点を当てた経営管理手法であり、サプライチェーンマネジメントはERPの一部といえます。
▹SCMを深く理解するために、「ロジスティクス」と「SCM」が目指す最適化の違いをチェック。
▹供給網全体の「SCM」に対し、自社の付加価値創造プロセスを分析する「バリューチェーン」の活用術。
サプライチェーンマネジメントを導入するメリット・デメリット
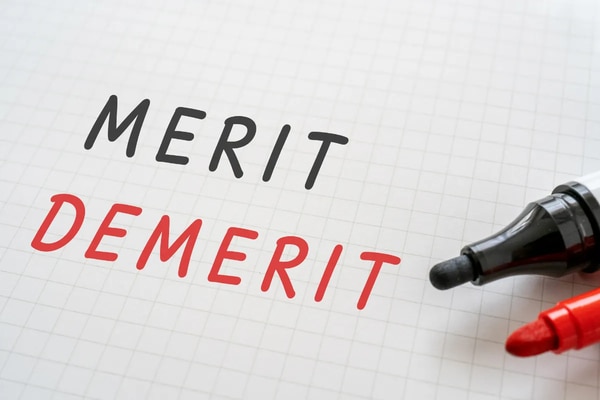
物流現場では、人材不足や新型コロナウイルスの影響を受け、サプライチェーンマネジメントを構築するニーズが高まっています。こちらでは、物流業務にサプライチェーンマネジメントを導入するメリット・デメリットをご紹介します。
サプライチェーンマネジメント導入のメリット
- リードタイムの短縮につながる
サプライチェーンマネジメントの導入によってサプライチェーン全体で情報を共有することで、各プロセスの連携がスムーズになるため、リードタイムが短縮され、商品の供給をスピーディーに行いやすくなります。リードタイムとは、商品の製造から発注、納品までにかかる総合的な時間のことです。
- 在庫を可視化し、適正化しやすい
サプライチェーンマネジメントの導入により各プロセスの情報を共有することで、需要予測が行いやすくなります。その結果、在庫の可視化・適正化に取り組むことができ、過剰在庫によるキャッシュフローの悪化、在庫切れによる販売機会の損失などを防止できます。
- コスト削減につながる
サプライチェーンマネジメントによって部分最適から全体最適の考え方にシフトできれば、必要なタイミングに必要な数量だけ商品を提供できます。そして、在庫量の適正化にもつながるため、在庫管理や返品、廃棄処理、不要な輸配送などにかかるコスト削減を実現可能です。
- 需要変動に迅速に対応しやすい
サプライチェーンマネジメントの導入によって各プロセスの情報を集約することで、市場分析や需要変動の予測がしやすくなります。戦略的な生産管理が可能になるため、利益の最大化も期待できます。
- 人的資源を有効活用しやすい
サプライチェーンマネジメントを導入して情報を一元管理することで、人的資源が不足している場所が明確になります。人手不足による残業時間や離職者の増加などを防止でき、業務効率の向上にも役立ちます。
サプライチェーンマネジメント導入のデメリット
- コストがかかる
サプライチェーンマネジメントを機能させるには、物流管理システムの導入やITによるインフラ整備が必須です。企業形態や業種などに応じて導入するシステムは変わるものの、規模が大きくなるにつれてコストは高くなる傾向にあります。また、導入費用だけでなく、保守や運用に関する人材も必要になります。システムやサービスの価格、解決したい課題などに応じて、最適なソリューションシステムや手法を選択することが重要です。
- 工程に関わる全企業の協力が必要になる
横断的な情報共有には、部品の供給元であるサプライヤー、商品の製造者であるメーカー、販売業者であるベンダーなど、サプライチェーンに関わるすべての企業の協力が欠かせません。イニシアチブを握る企業やリーダーがいないと、統率が難しくなるおそれがあります。また、部署間の協力体制が希薄な企業の場合、社内調整から始めなければならないケースもあります。
▹SCMの実現を加速させる、最新技術を用いた「物流DX」の概要と未来。
サプライチェーンマネジメント導入の流れ

サプライチェーンマネジメントは導入から効果が実証されるまでに時間がかかるため、多様化する物流ニーズに応えるためには、速やかな導入が必要です。以下では、サプライチェーンマネジメントを効率的に導入するための流れをご紹介します。
STEP1:サプライチェーンの課題を列挙し、目標を決める
サプライチェーンマネジメントをうまく機能させるには、現状のサプライチェーンにおける課題を明確にする必要があります。課題が不明確な状態だと、導入すべきシステムや重点的に取り組むべきポイントが判断できないためです。各業務プロセスに分けて課題を洗い出し、最終的な目標や指標を決めましょう。
STEP2:担当部署やリーダーなどを決める
サプライチェーンマネジメントを自社に浸透させるには、担当部署やリーダーなどを決めるのが効率的です。流通や物流に関する最新の知見を持ち、経営者視点で集約された情報を分析できる人材を選ぶのが良いでしょう。
STEP3:導入すべきシステムやサービスを比較検討する
最初に列挙した課題や目標をもとに、導入するシステムやサービスを決定しましょう。現在の業務実態や問題点に則したものを選ぶには、複数のサービスを比較検討することが大切です。
STEP4:導入後の効果について評価する
導入するサービスが決まったら、見込まれる効果について考察します。自社が抱える問題点を、サプライチェーンマネジメントの導入によってどの程度改善できるか検討する作業です。十分な効果が期待できるかだけでなく、コストに見合っているかなども確認しましょう。
サプライチェーンマネジメントで多様化する物流ニーズに柔軟に対応しよう
企業のグローバル化やビジネスモデルの変化などを受け、物流ニーズが多様化しています。そのため、サプライチェーンマネジメントの導入によって情報の共有、業務の効率化を図り、顧客からの注文に柔軟に対応できる環境を作り上げることが大切です。自社の課題や目標に合わせて、最適な形でサプライチェーンマネジメントの導入を進めましょう。
サプライチェーンマネジメントにおける物流課題の解決には、軽貨物で50,000台以上(バイク・自転車含む)、一般貨物(2トン~10トン車)で2,000社以上の登録台数を誇る配送マッチングサービス「ピックゴー」がおすすめです。24時間365日即日対応可能で、軽貨物から大型トラック、冷凍車まで多様な車種を短期間で提供できます。マッチングにかかる最短時間は56秒です(2023年3月現在)。



