
黒ナンバー任意保険を安くする方法|個人事業主向け完全ガイド
こんにちは。物流に関する知識をまとめたメディア「ピックゴー物流コラム」編集部です。
軽貨物配送を始めるにあたって、多くの方が頭を悩ませるのが「黒ナンバー車両の任意保険」。
「どんな補償が必要?」「自家用車の等級は引き継げる?」「費用はどのくらいかかるの?」──こうした疑問や不安は、始めたばかりの方だけでなく、経験者の方からも多く寄せられます。
今回はそんな声に応えるべく、黒ナンバー向け任意保険の選び方や注意点、さらに“保険料が安くなる裏ワザ”まで徹底解説!
ピックゴーならではの団体扱/集団扱割引や独自サポート制度もご紹介しますので、これから配送業を始める方も、すでに活躍中の方も必見です。
安心・安全な配送ライフの第一歩として、ぜひ参考にしてください!
※文中に掲載の内容は2025年12月時点の内容のため、今後、内容が変更になっている場合があります。
目次[非表示]
- 1.黒ナンバーとは?個人で使う軽貨物車の基本知識
- 1.1.黒ナンバーの定義と取得方法
- 1.1.1.事業用としての黒ナンバーの役割
- 1.1.2.軽自動車との違い(黄ナンバーとの比較)
- 1.2.個人事業主でも黒ナンバーは取得できる?
- 1.2.1.必要書類と手続きの流れ
- 1.2.2.営業ナンバーとしての注意点
- 2.黒ナンバー車に任意保険が必要な理由
- 2.1.自賠責保険だけでは補償が不十分
- 2.1.1.業務中の事故は賠償リスクが高い
- 2.1.2.荷主との契約で任意保険が求められるケースも
- 2.2.万が一の備えとして任意保険が必須
- 2.2.1.対人・対物補償の重要性
- 2.2.2.車両保険や特約の有無がビジネス継続を左右する
- 3.黒ナンバー任意保険の相場と高くなる理由
- 3.1.なぜ黒ナンバーの任意保険は高いのか?
- 3.1.1.型式別料率クラスが適用されない仕組み
- 3.1.2.業務使用のため事故リスクが高いとみなされる
- 3.2.保険料に影響する主な要因
- 3.2.1.型式別料率クラスが適用されない仕組み
- 3.2.2.使用目的(業務・日常)と走行距離
- 3.2.3.車両保険や特約の選択による変動
- 4.黒ナンバー任意保険を安くする5つのポイント
- 4.1.①:補償内容の見直し
- 4.1.1.本当に必要な補償だけに絞る
- 4.1.2.免責金額の設定で保険料を抑える
- 4.2.②:年払い/一括払いでの割引活用
- 4.3.③:等級の引き継ぎ制度を利用する(自家用→黒ナンバー)
- 4.4.④:不要な特約を外す
- 4.5.⑤:団体扱いや紹介制度のあるサービスを活用
- 5.個人事業主・軽貨物ドライバーにおすすめの保険の選び方
- 5.1.補償内容と保険料のバランスを見る
- 5.1.1.対人・対物は「無制限」が基本
- 5.1.2.車両保険の必要性は運用状況で判断
- 5.2.事故時のサポート体制を確認する
- 5.2.1.24時間の事故受付やロードサービス
- 5.2.2.示談交渉サポートの有無
- 5.3.黒ナンバー車に対応しているかを確認
- 5.4.通販型・代理店型の違いと選び方のポイント
- 6.黒ナンバー任意保険も対象!ピックゴーの「集団扱自動車保険」とは
- 6.1.パートナー専用の団体割引制度
- 6.1.1.通常より保険料が抑えられる仕組み
- 6.1.2.実際の保険料試算例とコスト感
- 6.2.配送事業者に特化した安心の補償内容
- 6.2.1.「安全保証バッジ」などの独自制度
- 6.3.任意保険以外にも手厚い支援
- 6.3.1.車検・整備・代車サポート
- 6.3.2.保険以外のメンテナンスも一本化可能
- 7.ピックゴーの集団扱自動車保険お申し込みの流れ
- 7.1.ドライバー登録と申請手順
- 7.2.配送業務前の加入が必須である理由
- 8.黒ナンバー任意保険に関するよくある質問(FAQ)
- 8.1.Q. 自家用車の保険等級を引き継げますか?
- 8.2.Q. 車両保険は絶対につけるべきですか?
- 8.3.Q. 黒ナンバー任意保険はすぐに加入できますか?
- 8.4.Q. 加入中の保険が満期前だが切り替えできますか?また、その際の保険料はどうなりますか?
- 9.黒ナンバーの任意保険、迷うなら「今」が動き出すタイミング!
黒ナンバーとは?個人で使う軽貨物車の基本知識

軽貨物配送で独立を目指す方、すでにドライバーとして活躍中の方、黒ナンバーについてしっかり理解できていますか?「なんとなく必要そう…」という認識では、あとあとトラブルの元になるかもしれません。
結論から言えば、黒ナンバーは個人事業主が軽貨物車で営業活動を行うために必須のものです。
この記事では、その定義や取得方法、黄ナンバーとの違いまでを丁寧に解説していきます。
これを読めば、「なぜ必要なのか?」「どうやって取得するのか?」がスッキリ理解できますよ。
まずは「黒ナンバーの基本的な定義と取得方法」から見ていきましょう!
黒ナンバーの定義と取得方法
黒ナンバーとは、軽貨物車両を営業目的で使用する際に必要なナンバープレートのことです。
ナンバープレートの地名の右に黒い背景に黄文字で数字が記載されているのが特徴です。
なぜ黒ナンバーが必要なのかの理由はシンプルで、営業用として軽貨物車を使うなら、道路運送法に基づいて適切な登録が必要だからです。
例えば、荷主から報酬をもらって荷物を運ぶ行為は「営業」とみなされ、黒ナンバーがないと違法になります。
取得の流れは以下の通りです
運輸支局で「貨物軽自動車運送事業」の届出をする
必要書類を提出(後述)
問題なければ、届出受理証明書が交付される
軽自動車協会で黒ナンバー交付の手続きを行う
ナンバープレートは、通常の自動車とは異なり「営業車両用」として扱われるため、保険や車検にも影響があります。
それでは次に、黒ナンバーが担う「事業用としての役割」について詳しく見ていきましょう!
事業用としての黒ナンバーの役割
黒ナンバーの最大の役割は、個人でも合法的に軽貨物配送ビジネスを始められるという点です。
例えば、Uber Eats や Amazon Flex などの配送業務に従事するには、ほとんどの場合で黒ナンバーの取得が必須とされています。
これは報酬を得る業務であるため、法的に営業用の登録が求められるからです。
黒ナンバーは単なるプレートではなく、「この車はビジネスで使っています」という証でもあります。
つまり、信頼性にも関わる重要な要素なのです。
次は、同じ軽自動車でも異なる「黄ナンバー」との違いについて整理してみましょう!
軽自動車との違い(黄ナンバーとの比較)
黒ナンバーとよく混同されるのが、一般の軽自動車が使っている黄ナンバーです。
比較項目 | 黒ナンバー | 黄ナンバー |
|---|---|---|
用途 | 営業用(報酬を伴う配送など) | 自家用(通勤・買い物など) |
登録の手続き | 運輸支局で営業届出が必要 | 通常の軽自動車登録 |
任意保険 | 事業用保険が必要 | 自家用車用保険 |
違いを一言でまとめると、「お金をもらって荷物を運ぶなら黒ナンバー」ということです。
さて、「法人じゃないと黒ナンバーって取れないの?」と不安になる方もいるかもしれません。次は、個人事業主が黒ナンバーを取得できるのかについて解説します!
個人事業主でも黒ナンバーは取得できる?
もちろん個人事業主でも黒ナンバーは取得できます!
実際に、全国で軽貨物ドライバーとして活躍している方の多くは個人事業主です。
ただし、届出の際にはいくつかの書類や準備が必要です。
法人でなくても、しっかりルールを守っていれば誰でも始められます。
次の項目で、黒ナンバー取得に必要な書類や手続きの流れを見てみましょう!
必要書類と手続きの流れ
黒ナンバーの届出に必要な主な書類は以下の通りです。
運送事業届出書
使用する車両の車検証のコピー
使用する営業所・休憩施設の情報
届出後、問題がなければ即日または数日で「届出受理証明書」が交付されます。この証明書を持って陸運局に行き、ナンバープレートを黒ナンバーに変更します。
行政手続きが苦手な方でも、代行サービスを使えばスムーズに取得できますよ。
ただし、営業として車を使う以上、守るべきルールや注意点も存在します。次は、営業ナンバーとしての注意点について見ていきましょう!
営業ナンバーとしての注意点
黒ナンバーを取得すれば終わりではありません。
運用ルールを守らないと罰則や登録取り消しのリスクもあります。
特に注意したいポイントは以下の通りです。
業務使用中の自家用用途での使用は禁止(家族の送迎や買い物など)
定期的な車両点検や記録の義務がある
任意保険も「事業用」に対応したものを選ぶ必要あり
営業範囲や車両の使用用途の記録が必要
違反が発覚すると、最悪の場合は黒ナンバーを返納しなければならなくなる可能性も。きちんとルールを守ることで、安全で安定した配送業務が実現できます。
では次に、「なぜ黒ナンバー車にも任意保険が必要なのか?」
その理由について詳しく解説していきます!
黒ナンバー車に任意保険が必要な理由

黒ナンバーを取得して配送業務を始めたなら、次に必ず考えるべきなのが「任意保険」です。
結論から言うと、黒ナンバー車に任意保険は必須です。
自賠責保険だけではカバーしきれないリスクが多く、万が一の事故が事業の継続を脅かす可能性もあるからです。
この章では、自賠責保険と任意保険の違いや、なぜ任意保険が必要なのかを分かりやすく解説していきます。
まずは「自賠責保険だけでは補償が不十分」な理由から見ていきましょう!
自賠責保険だけでは補償が不十分
自賠責保険(強制保険)は、すべての車両に加入が義務づけられている基本的な保険です。
しかし、これは対人事故(ケガ・死亡)に対する最低限の補償しか含まれていません。
たとえば、自賠責保険で補償される上限は以下のとおりです。
補償内容 | 上限額 |
|---|---|
死亡事故 | 最大3,000万円 |
傷害(ケガ) | 最大120万円 |
重度後遺障害 | 最大4,000万円 |
一見十分なように見えるかもしれませんが、実際にはこれで足りないケースが多発しています。
業務中の事故は賠償リスクが高い
営業中の事故は、一般のドライブと比べて「責任の重さ」が違います。
なぜなら、配送先の会社や荷主の信頼を損ねるだけでなく、業務に支障が出たり、法的な責任を問われるリスクがあるからです。
例えば
交差点で歩行者をはねてしまい、後遺障害が残った
高級車と接触してしまい、修理費用が数百万円かかった
積み荷が破損し、荷主から損害賠償請求された
このような事態になっても、自賠責保険では到底まかないきれません。
だからこそ、業務で使う車には対人・対物の任意保険が欠かせないのです。
荷主との契約で任意保険が求められるケースも
さらに最近では、荷主企業との契約条件として任意保険の加入を求められるケースも増えています。
特に大手ECサイトや宅配業者と提携する場合、以下のような条件を提示されることがあります。
対人・対物無制限の保険加入
車両保険への加入(またはそれに代わる補償制度)
事故時の連絡体制の明記
これは、荷主側も事故による損失を避けるため、万全なリスク管理を求めているからです。
任意保険の有無が、仕事を受けられるかどうかに直結することもあるんです。
次は、こうした背景を踏まえて「万が一の備えとして任意保険が必須である理由」をさらに詳しく見ていきましょう!
万が一の備えとして任意保険が必須
黒ナンバーで配送業務をする以上、「もしもの事故」は避けられないリスクです。
だからこそ、任意保険はビジネスを守る“セーフティーネット”として必須となります。
対人・対物補償の重要性
一番大切なのは、やはり対人・対物の無制限補償です。
人身事故では、被害者への賠償金が数千万円から億単位に達することも珍しくありません。
また、相手が高級車や店舗であれば、修理費や営業損失の請求が多額の費用となる場合があります。
仮に補償が足りなければ、不足分は自己負担になります。そうなれば、個人事業の継続どころか、生活そのものが破綻しかねません。
だからこそ、「対人・対物無制限」が今や業界のスタンダードなんです。
車両保険や特約の有無がビジネス継続を左右する
さらに、任意保険には「車両保険」や「特約」もつけることができます。
例えば
車両保険:事故や災害で車が壊れても修理費を補償(加入タイプによっては範囲の制限あり)
臨時代替自動車特約:契約自動車が整備・修理・点検等の為に使用できない間、臨時に借り入れた臨時代替自動車を契約自動車と見なして補償が受けられる
弁護士費用特約:トラブル時の法的対応をサポート
これらの特約があることで、事故後も仕事を止めずに対応できるようになります。
事業を止めずに継続するためには、こうした備えが非常に重要です。
それでは次に、気になる「黒ナンバー任意保険の保険料はなぜ高いのか?」という疑問について詳しく見ていきましょう!
黒ナンバー任意保険の相場と高くなる理由

「黒ナンバーの任意保険って、なんでこんなに高いの!?」と驚いたことはありませんか?
結論から言えば、黒ナンバーの任意保険は“業務用”だから高いのです。
使用環境やリスクが自家用車と大きく異なるため、保険会社側も慎重に保険料を設定しているんですね。
この章では、なぜ黒ナンバー保険料が高くなるのか、その理由や仕組みをわかりやすく解説していきます。
まずは、「そもそもなぜ高いのか?」という根本的な仕組みから確認していきましょう!
なぜ黒ナンバーの任意保険は高いのか?
黒ナンバーの任意保険が高くなる理由は、ズバリ保険会社がリスクを高く見積もっているからです。
保険とはリスクに応じて料金が決まるサービスなので、当然といえば当然です。
型式別料率クラスが適用されない仕組み
一般的な自家用車では「型式別料率クラス」という制度が使われています。
これは、車種ごとの事故率や修理費などに応じて保険料が調整される仕組みで、リスクの少ない車種は保険料が安くなる仕組みです。
ところが黒ナンバー車にはこの料率クラスが適用されません。
業務用途というだけで一括りにされ、リスクが高い前提で保険料が設定されてしまうのです。
業務使用のため事故リスクが高いとみなされる
もうひとつの理由は、日常的に長時間・長距離を運転するため、事故に遭う確率が高いとされていることです。
実際、国土交通省の「貨物自動車交通事故統計」によると、営業用軽貨物車の事故率は自家用車より高めの傾向にあります。
例えば
自家用軽自動車の年間事故率:約1.2%
営業用軽貨物車の年間事故率:約1.8%
この差が、保険料にもそのまま反映されているというわけです。
だからこそ、黒ナンバーの任意保険は「高い」のではなく、「業務リスクを反映した妥当な価格」とも言えるのです。
では次に、実際の保険料を左右する「主な要因」を見ていきましょう!
保険料に影響する主な要因
黒ナンバーの保険料が高くなるのは、さまざまな条件によっても左右されます。
特に影響が大きいのは、運転者の属性や車両の使い方、補償内容の選び方です。
型式別料率クラスが適用されない仕組み
運転者が若ければ若いほど、保険料は高くなります。
これは、事故率の高い年齢層(特に18〜24歳)がリスクとして見なされるからです。
また、自動車保険には「等級制度」という仕組みがあり、無事故で保険を継続すると等級が上がり、保険料が割引されていきます。
逆に、事故を起こすと等級が下がり、保険料が大幅にアップします。
等級 | 割引率(目安) |
|---|---|
20等級 | 63%割引 |
6等級(初年度) | 3%割増 |
1等級 | 108%割増 |
もし自家用車で保険に加入していた経験があれば、その等級を引き継ぐことで保険料を下げられる可能性もあります。
使用目的(業務・日常)と走行距離
保険会社は「使用目的」も保険料に大きく関わる項目です。
日常使用よりも業務使用のほうがリスクが高いと判断され、保険料が高くなります。
さらに、年間の走行距離もポイント。
走行距離が長い=事故に遭う確率も高くなるため、距離が多ければ多いほど保険料が高くなります。
目安としては
年間1万km未満:標準的な保険料
年間2万km以上:割増される可能性あり
車両保険や特約の選択による変動
任意保険には「車両保険」や「各種特約」をつけることで、さらに補償を手厚くすることができますが、その分保険料も上乗せされます。
たとえば
車両保険:+数万円/年
弁護士費用特約:+数千円/年
代車費用特約:+数千円/年
とはいえ、事故の際に助かるのもこうした特約なので、コストとリスクを天秤にかけて検討することが重要です。
さて、ここまでで「なぜ高いのか」が分かったところで、次は「どうすれば保険料を安くできるのか?」という対策を具体的に紹介していきます!
黒ナンバー任意保険を安くする5つのポイント

「黒ナンバーの保険って高いな…でも、少しでも安くしたい!」
そう思っているなら、保険料を下げるための具体的な工夫を知っておきましょう。
結論から言うと、補償内容や契約方法を見直すことで、無理なく保険料を節約できます。
ここでは、黒ナンバー任意保険を安くするための6つの実践ポイントを紹介します。
まずは、一番効果的な「補償内容の見直し」から確認していきましょう!
なお、こちらの『事業用自動車保険を安くする方法|コスト削減のポイントと補償の選び方』でも詳しく解説していますので、併せてお読みください。
①:補償内容の見直し
任意保険は、補償が手厚ければ手厚いほど保険料も高くなります。
だからこそ、本当に必要な補償だけに絞ることで、保険料をグッと抑えることができるんです。
本当に必要な補償だけに絞る
例えば、「車両保険」は車をぶつけたときの修理費を補償してくれる便利な保険ですが、年式の古い車や買い替え予定の車両には不要な場合もあります。
また、「搭乗者傷害保険」や「人身傷害保険」も、自賠責と重複する場面があるため、内容をよく確認しましょう。
見直しのポイント
車両保険:年式が古いなら外す選択もあり
搭乗者傷害:人身傷害と重複していないか確認
対人・対物補償:無制限は維持が基本
免責金額の設定で保険料を抑える
「免責金額(自己負担額)」を設定することで、保険料を下げることもできます。
たとえば、車両保険において「免責5万円」と設定すれば、毎年の保険料が数千円〜1万円ほど安くなることも。
「事故はめったに起こさないけど、万一のときだけ備えたい」という方には、特におすすめの節約法です。
では次に、「支払い方法を工夫するだけで得する方法」を見ていきましょう!
②:年払い/一括払いでの割引活用
任意保険は月払いよりも年払い・一括払いの方が約5%程度お得になっています。
具体的には
支払方法 | 年間保険料(例) |
|---|---|
月払い | 約90,000円 |
年払い | 約85,000円 |
年払いにするだけで、年間5,000円程度も安くなる場合があるんです!
「資金に余裕がある月にまとめて払う」というだけで、確実に節約できますよ。
次は、これまで乗っていた自家用車の保険等級をうまく活用する方法を紹介します!
③:等級の引き継ぎ制度を利用する(自家用→黒ナンバー)
今まで自家用車で保険に入っていた方は、その等級を黒ナンバー保険に引き継げる制度を活用しましょう。
等級とは「保険の優良ドライバー度」を表す数字で、無事故で年数を重ねると最大で20等級(約60%割引)まで上がります。
例えば
自家用車で10等級 → 黒ナンバーに切り替えても10等級スタートOK(同一契約者かつ同一車両に限る)
新規で加入(6等級)との差額:約20%以上
この制度を知らずに6等級からスタートしてしまうと、初年度の保険料が大きく損してしまいます。
等級の引き継ぎは保険会社や代理店に必ず確認してくださいね!
それでは次に、運転者の「年齢や範囲」を見直して保険料を下げる方法を紹介します!
④:不要な特約を外す
便利そうだからといって、何でもかんでも特約を付けていませんか?
実はこの「特約」、積み重ねると意外と高額になるんです。
たとえば
特約内容 | 年間保険料の目安 |
|---|---|
弁護士費用特約 | 約3,000円 |
代車費用特約 | 約4,000円 |
搭乗者傷害特約 | 約2,000円 |
必要なものだけを選べば、年間5,000〜10,000円の削減も可能。
とくに他の保険やサービスですでにカバーされている内容は、重複に要注意です。
最後に、特に見逃せない黒ナンバードライバー向けの団体扱/集団扱割引制度について紹介します!
⑤:団体扱いや紹介制度のあるサービスを活用
黒ナンバー向けの任意保険には、団体扱/集団扱割引制度を活用できるケースがあります。
中でも、配送マッチングサービス「ピックゴー」のような企業が提供している団体扱/集団扱自動車保険は、特に注目したい節約手段です。
なぜなら、通常よりも保険料が大幅に安くなることがあるからです!
さらに
加入手続きがアプリで簡単
専用サポートが受けられる
配送業務向けの特約が標準で付いている
など、料金面だけでなく「使いやすさ」「安心感」においても魅力があります。
ここまでで、保険料を安くするための方法がいろいろ見えてきましたね!
次は、「実際にどんな保険を選べばいいのか?」軽貨物ドライバーにおすすめの選び方を紹介していきます!
個人事業主・軽貨物ドライバーにおすすめの保険の選び方

黒ナンバー車を使用する個人事業主や軽貨物ドライバーにとって、任意保険は“仕事の命綱”とも言える存在です。
だからこそ、「どの保険を選べば安心か?」を知っておくことがとても大切です。
この章では、保険を選ぶ際にチェックすべきポイントをわかりやすく解説していきます!
なお、こちらの『黒ナンバーの任意保険|個人事業主が失敗しない格安プランの選び方』でも詳しく解説していますので、ご興味のある方はお読みください。
補償内容と保険料のバランスを見る
任意保険は、安ければいいというものではありません。
事故が起きたときに「備えておけばよかった…」と後悔しないよう、補償と費用のバランスを取ることが大切です。
例えば、補償が手厚すぎると保険料が跳ね上がりますが、逆に最低限にすると、事故時の負担が大きくなります。
つまり、“安心できる範囲の補償を、無理のない価格で”が理想です。
では、実際に見直すべき補償内容を詳しく見ていきましょう!
対人・対物は「無制限」が基本
対人・対物補償は、万が一の重大事故にも対応できるよう「無制限」にするのが基本です。
というのも、実際にあった事故では、以下のような高額な賠償事例があります。
事故の種類 | 損害額 |
|---|---|
歩行者への衝突事故 | 約3億円 |
高級車との接触事故 | 約1,200万円 |
このように、賠償額は数千万円〜数億円にのぼるケースも少なくありません。
「無制限」にしておけば、どれだけ大きな事故でも自己負担を避けられますよ。
では次に、意外と見落としがちな「車両保険の要・不要」について解説します。
車両保険の必要性は運用状況で判断
車両保険は、「自分の車の損害」に備えるものです。
業務用で毎日走行するドライバーには心強い味方ですが、実は全員に必要とは限りません。
たとえば…
車両価格が低い → 修理費より保険料の方が高くつくことも
買い替え予定が近い → 保険料がもったいない
こうした場合は、車両保険を外すことで大幅なコストダウンが可能です。
「どれくらい稼働しているか」「車を買い替える予定があるか」など、自分の状況をもとに判断しましょう。
では次に、いざというときの安心材料「事故対応サービス」についてご紹介します!
事故時のサポート体制を確認する
どれだけ安全運転を心がけていても、事故は突然起きてしまうもの。
そんな時、頼れる保険会社かどうかが大きな違いを生みます!
「契約して終わり」ではなく、事故発生時にしっかりサポートしてくれるかを事前にチェックしておきましょう。
では具体的にどんなサポートが重要なのか、次の項目で見ていきます。
24時間の事故受付やロードサービス
事故が夜間や早朝に起きたらどうしますか?
そんなとき頼りになるのが「24時間365日対応」の事故受付とロードサービスです。
以下のサービスが備わっていると安心です。
24時間の事故受付窓口
現場へのレッカー手配
応急処置や代車手配の対応
これらの対応が迅速であるかどうかが、その後の業務への影響を左右します。
ドライバーとしての安心感がぐっと高まりますよ。
続いては、意外と見落としがちな「示談交渉サービス」についてお伝えします!
示談交渉サポートの有無
事故の後で一番ストレスになるのが、相手とのやりとり。
そんなとき保険会社が「示談交渉」を代行してくれるかどうかは非常に重要です。
示談交渉サービスがあると…
相手方とのやりとりをすべて任せられる
法律知識がなくても安心できる
時間と手間が大幅に省ける
これがあるだけで、精神的な負担が大きく変わります!
事故対応が不安な方は、必ずチェックしておきましょう。
それでは次に、実は見落としがちな「黒ナンバー対応かどうか」のチェックポイントに移ります。
黒ナンバー車に対応しているかを確認
任意保険は、どれでも黒ナンバーに対応しているわけではありません。
個人事業主や軽貨物ドライバー向けの特殊なニーズに対応していない保険も多いのです。
黒ナンバー対応の保険を選ばないと…
万一の事故で補償対象外になる
業務用としての条件が合わず契約できない
といったトラブルの原因になります。
申込み前に「この保険は黒ナンバー車でも使えるか?」を必ず確認してくださいね!
では最後に、「通販型と代理店型の違い」について見ていきましょう。
通販型・代理店型の違いと選び方のポイント
保険には「通販型」と「代理店型」の2種類があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分のスタイルに合った方を選びましょう!
種類 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
通販型 | ネットで完結・保険料が安い | コスト重視・ネット操作が得意 |
代理店型 | 対面で相談・サポートが手厚い | 初心者・対人サポート重視 |
例えば、保険の仕組みがよく分からないという方は、代理店型でじっくり相談しながら決めるのがおすすめです
以上が保険選びの基本となるポイントです。
次の章では、実際に人気の任意保険を比較しながら、それぞれの特徴をチェックしていきましょう!
おすすめの補償内容については、『4ナンバー任意保険の選び方|おすすめ補償と安くする方法』でも詳しく解説していますので、併せてお読みください。
黒ナンバー任意保険も対象!ピックゴーの「集団扱自動車保険」とは

黒ナンバーの任意保険料が高くて悩んでいる方に朗報です!
配送業に特化したピックゴーでは、パートナー限定で保険料をグッと抑えられる「集団扱自動車保険」制度を用意しています。
補償内容はそのままに、コストを下げられるのが最大の魅力です。
では、どのような仕組みで保険料が安くなるのか、詳しく見ていきましょう。
パートナー専用の団体割引制度
ピックゴーの集団扱自動車保険は、配送パートナー向けの集団扱割引制度が魅力です。
集団扱とは、所定の要件を充足する下請業者の団体または同一業者の団体を主な対象の範囲としています。
所定の要件については、下記の通りとなります。
ア.同一の共通目的をもつ者のみによって組織されていること。
イ.集団の構成員が常時明確に把握されており代表者の定めがあること。
ウ.会計帳簿等が整備されていること。
エ.保険加入のみを目的として組織されていないこと。
上記を満たす場合にこの割引制度の使用ができ、さらには配送に特化した補償もセットになっているため、業務に最適な保険が利用できます。
次の章では、具体的な保険料の試算例を交えながら、実際のコスト感を詳しくご紹介します!
通常より保険料が抑えられる仕組み
ピックゴーの「集団扱自動車保険」は、個人では加入できない団体扱/集団扱割引制度です。
たとえば、個人で加入すると年間保険料が12万円かかるプランでも、団体扱なら約5%オフ11万4,000円で済むことも。
この差額は1年で6,000円、5年でなんと3万円もの節約に!
このように、団体割引制度を活用することで、同じ補償内容でも保険料を大きく下げることができるのです。
次は、実際にどれくらい安くなるのか、保険料の試算例をご紹介します。
実際の保険料試算例とコスト感
「本当に安くなるの?」と気になる方も多いはず。
そこで、軽貨物車(黒ナンバー)に乗る30代ドライバーの試算例をご紹介します。
加入形態 | 年間保険料(目安) | 補償内容 |
|---|---|---|
個人契約 | 約120,000円 | 対人・対物無制限、車両保険あり |
ピックゴー団体扱 | 約114,000円 | 同上(補償内容は変わらず) |
このように、同じ内容でも年間でガソリン代満タン給油相当の差が出ることがあります。
特に配送業で年間走行距離が多くなる方には、大きな節約につながりますね。
では、なぜここまで配送業に特化できるのか?
次の章では、補償内容の特徴を見ていきましょう。
配送事業者に特化した安心の補償内容
ピックゴーの集団扱自動車保険は、配送事業者向けに必要な補償内容を提案できることが特徴です。
配送プラットフォームを運営しているノウハウを活かし、業務中の事故やトラブルをしっかりカバーするため、一般的な保険では対応しきれないリスクに対するご提案が可能です。
また、配送のプロが安心して働けるように、対人・対物賠償も充実した補償が用意されています。
これにより、配送中の様々なリスクからドライバーを守り、安心して業務に集中できる環境をサポートしているのです。
「安全保証バッジ」などの独自制度
ピックゴーでは、一定の条件を満たしたドライバーに対して「安全保証バッジ」を発行。
これは、安全運転を継続し、保険事故が少ないドライバーを評価する制度です。
こうした制度により、日々の安全運転が「仕事」と「保険料」の両面でプラスに働く仕組みになっているのです。
では、ピックゴーのサポートは保険だけなのでしょうか?
次は、任意保険以外のサポートについてご紹介します。
任意保険以外にも手厚い支援
ピックゴーは、任意保険だけでなく配送事業者を総合的にサポートする体制が充実しています。
車検や整備のサポート、さらに万が一の際の代車提供まで、業務を止めないためのサービスが揃っているのが強みです。
これにより、車両のトラブルで配送が遅れる心配を軽減。
保険以外のメンテナンスも一括して依頼できるので、手間やコストの節約にもつながります。
配送に集中したいドライバーにとって、こうしたサポートは大きな安心材料となるでしょう。
車検・整備・代車サポート
ピックゴーでは、任意保険にとどまらず、車検や整備、代車の手配までトータルでサポートしています。
「車が故障した!でも明日も配送がある…」そんなピンチでも、代車サポートで業務を止めずに済むのは心強いポイントです。
また、定期的な車両メンテナンスも提携工場で対応可能。
割引価格で受けられるため、維持コストもぐっと抑えられます。
次は、保険だけでなく車両管理まで一元化できるメリットをご紹介します。
保険以外のメンテナンスも一本化可能
ピックゴーのサービスを利用すれば、保険・車検・修理などをまとめて一本化できます。
あちこちに連絡する手間が減り、忙しいドライバーの業務負担を軽減してくれます。
とくに個人事業主の方は、事務処理や整備管理に時間を取られがち。
ピックゴーを活用すれば、これらをまるっとお任せでき、配送に集中できる環境が整います。
さて、ここまで読んで「ぜひ活用してみたい」と思った方もいるのでは?
最後に、ピックゴーの「集団扱保険」について詳しく知る方法をご案内します!
ピックゴーの集団扱自動車保険お申し込みの流れ

「保険の申し込みって難しそう…」そんな不安をお持ちの方も、ご安心ください!
ピックゴーの集団扱自動車保険は、スマホから簡単に申し込めるうえ、サポート体制も万全です。
ここでは、申し込みの流れや必要な手順について、わかりやすくご紹介します。
ドライバー登録と申請手順
ピックゴーの保険制度を利用するには、まずドライバーとしての登録が必要です。
登録から保険申し込みまでは、すべてスマホアプリから完結できます。
具体的な流れは以下のとおりです。
▼お申し込みの手順
具体的な保険申し込みの流れは、以下の4ステップです。
「集団扱自動車保険」サービスサイトへ遷移
ページ内の「1分で完了!お見積もりはこちら」をクリック
必要情報の入力・書類提出
前述の情報と書類をアップロードして申し込みます。
窓口との契約手続き
提示された見積もり内容を確認し、契約手続きを実施する
証券もしくは契約内容控を受け取る
通常、契約後7~10日ほどでお手元に届きます。
アプリ操作に不慣れな方でも迷わないよう、画面にはステップごとのガイドが表示されるため安心です。
では、加入後はどんなサポートが受けられるのでしょうか?次で詳しく見ていきましょう。
配送業務前の加入が必須である理由
ピックゴーの集団扱保険に加入するには、配送業務を開始する前に手続きを完了させる必要があります。
これは、すべてのドライバーが公平に保険の恩恵を受けられるようにするため、そして万が一の事故にしっかり備えるためです。
というのも、配送中のトラブルや事故はいつ起きてもおかしくありません。
もし未加入の状態で事故が発生すると、保険で補償されず、自己負担が大きくなってしまう可能性も。
事前に加入しておくことで、
トラブル時も迅速に対応可能
補償内容が確定していて安心
依頼主にも「信頼できるドライバー」として印象アップ
このような利点があります。
だからこそ、配送を始める前にしっかり準備しておくことが大切なのです。
黒ナンバー任意保険に関するよくある質問(FAQ)
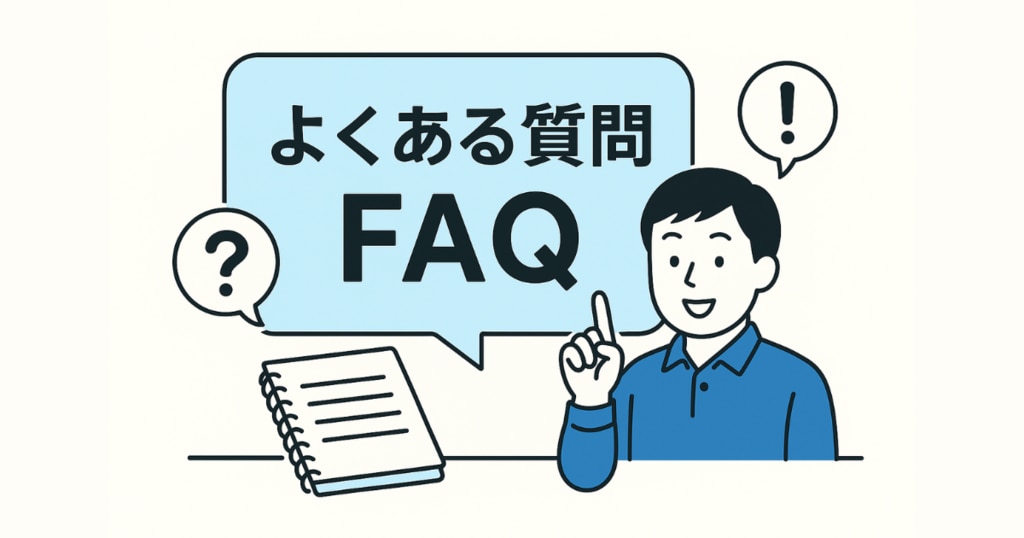
ここでは、ピックゴーをご利用いただく中で、ドライバーの皆さまからよく寄せられる「黒ナンバー任意保険」に関するご質問にお答えします。
加入を検討中の方や、保険について少し不安を感じている方も、ぜひチェックしてみてください!
Q. 自家用車の保険等級を引き継げますか?
結論から言うと、条件を満たせば引き継ぎは可能です。
ただし、すべてのケースで自動的に引き継げるわけではないため、注意が必要です。
保険等級とは、無事故で保険を継続してきた年数に応じて割引率が高くなる制度のこと。
例えば「20等級」であれば最大63%の割引が適用されることもあります(2025年時点の一般的な割引率)。
この等級は「同一の契約者」が「用途・車種の条件」を満たす場合に限り、商用車(黒ナンバー)に引き継げることがあります。
等級が引き継げる主な条件
自家用車から商用車へ名義変更がない(同一人物が契約)
現在の任意保険が継続中または解約から13か月以内
新たな保険会社が等級の引き継ぎを認めている
保険会社によって対応が異なるため、事前に確認することをおすすめします。
もし等級の扱いに不安がある場合は、次の質問も参考にしてみてください!
Q. 車両保険は絶対につけるべきですか?
絶対ではありませんが、仕事で車を使うなら加入を強くおすすめします!
車両保険とは、自分の車が壊れたときに修理費を補償してくれる保険のこと。
相手への賠償をカバーする「対人・対物保険」とは異なり、自分の損害を補償するのが大きな特徴です。
配送中はどうしても運転頻度が多く、以下のようなリスクが高くなります。
狭い道や駐車場での接触事故
雨の日のスリップ事故
荷物積み下ろし時の傷や破損
実際、損保協会の調査によると、業務用車両における車両事故の発生率は一般乗用車の約1.4倍ともいわれています(2024年・全国平均データ)。
もちろん、車両保険をつけると保険料は上がりますが、「万が一」の出費を回避できる安心感は大きいです。
迷ったらまずは見積もりを取り、保険料とのバランスを比較して判断してみましょう。
Q. 黒ナンバー任意保険はすぐに加入できますか?
はい、必要書類がそろっていれば、最短即日で加入できます。
ピックゴーの「集団扱自動車保険」は、ドライバー登録から保険見積もり依頼までアプリ上で完結する仕組み。
そのため、店舗などへ足を運ぶ手間もなく、スマホひとつでスムーズに手続きが可能です。
加入までに必要な書類は以下のとおりです。
運転免許証の画像
車検証の画像(軽貨物車両に限る)
任意保険の申込同意(アプリ上でOK)
これらがそろっていれば、申請から1〜3営業日ほどで保険証券が発行されます。
業務開始前に余裕を持って準備すれば、万が一のトラブル時にも安心です!
Q. 加入中の保険が満期前だが切り替えできますか?また、その際の保険料はどうなりますか?
結論:途中解約して切り替えることができます。保険料は月割りで返金されるケースが多いです!
現在の保険に加入中でも、新しい任意保険に切り替えることは可能です。
一般的には「中途解約」という扱いになりますが、未経過分の保険料は月割りで返金されるため、損をする心配は少ないです。
ピックゴーでは、切り替えサポートも行っており、現在の契約状況に応じたアドバイスを受けることができます。
今の保険が自分に合っていないと感じたら、遠慮なくご相談ください。
黒ナンバーの任意保険、迷うなら「今」が動き出すタイミング!

ここまで、黒ナンバー車両に必要な任意保険の選び方や、よくある疑問への回答をお届けしてきました。
「業務用だから保険料が高そう…」「そもそもどれが必要なの?」といった不安も、少しずつクリアになったのではないでしょうか。
配送の仕事では、毎日が運転の連続です。ちょっとした油断が事故につながることもありますし、その時に頼れる保険があるかどうかは大きな違いです。
とくに、ピックゴーの「集団扱任意保険」なら、配送業初心者の方でも安心。登録から見積もり、見積もり依頼までアプリひとつで完結するので、手間も少なくてとてもスムーズなんです!
特におすすめしたいポイントは以下のとおり
月々の保険料が割安(団体扱/集団扱割引が適用)
自家用車から等級の引き継ぎもOK(条件あり)
スマホから申し込み可能で、最短即日スタート
車両保険や対人・対物賠償も自由に選べる
配送に特化した補償内容で万が一も安心
任意保険は“もしも”の備えだけでなく、「安心して仕事に集中できる環境」を手に入れるためのもの。
これから軽貨物配送を始める方や、保険の見直しを考えている方は、この機会にぜひ一度、ピックゴーの保険プランをチェックしてみてください!
さあ、安心と一緒に、次の配送へ出発しましょう!
なお、こちらの『黒ナンバーの任意保険|個人事業主が失敗しない格安プランの選び方』でも詳しく解説していますので、ご興味のある方はお読みください。
また、おすすめの補償内容については、『4ナンバー任意保険の選び方|おすすめ補償と安くする方法』でも詳しく解説していますので、併せてお読みください。
事業用自動車保険については、『事業用自動車保険を安くする方法|コスト削減のポイントと補償の選び方』でも詳しく解説しています。
SJ25-14298(2026/02/06)





